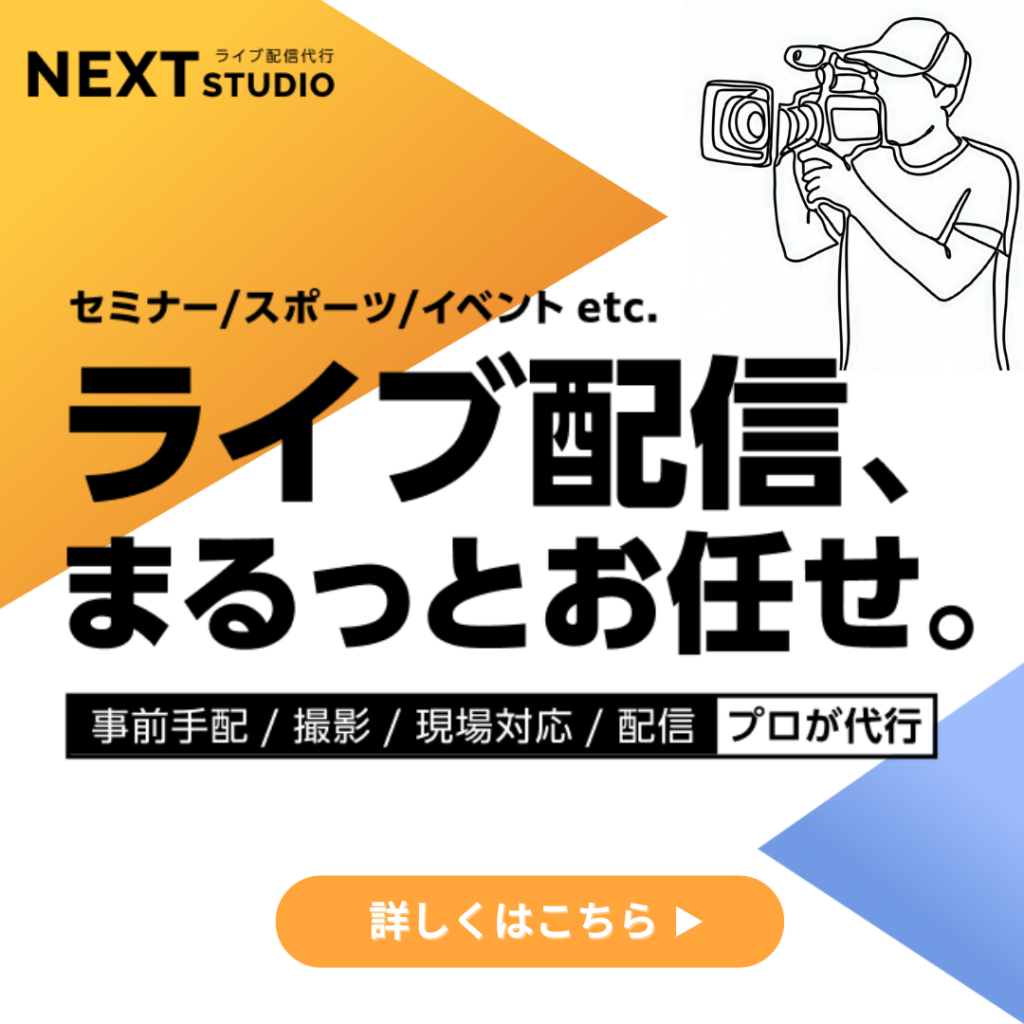ライブ配信導入を社内で提案する前に確認したい「よくある失敗」と「実例」
ライブ配信の活用は、今やマーケティングや社内イベント、採用活動など幅広いビジネスシーンで注目を集めています。しかし、初めての導入時に「なんとなく進めてしまった」「詳しい知識がないまま現場任せにした」ことで、失敗やトラブルを経験した企業も少なくありません。
この記事では、**社内提案の説得力を高めるために知っておきたい「よくある失敗とその原因」**をまとめてご紹介します。実際の配信支援会社や事例で挙げられる傾向をもとに、対策ポイントまで詳しく解説していきます。
ライブ配信について、詳しく知りたい方はこちらのブログ記事「ライブ配信とは?初心者でもわかる仕組み・活用事例・始め方を徹底解説」もぜひご覧ください。

企業が知っておくべきライブ配信で“よくある失敗とその原因”
映像が途切れる・画質が乱れる問題
ライブ配信における最も多いトラブルのひとつが、「映像が途中で止まる」「画質が荒れて視聴に耐えない」といった問題です。
特に、ZoomやYouTube Liveなどクラウド配信の場合、アップロード(上り)回線速度が20~30Mbps未満の場合に途切れやすくなる傾向があります。
主な原因:
- 安定しないWi-Fi回線を利用
- 配信場所における回線混雑(共用ネット回線)
- カメラやキャプチャ機器の設定不備
対策:
- 有線LAN接続+配信用の専用回線の確保(ホテルやイベント会場では特に重要)
- 事前テスト配信による画質・回線確認
- カメラ設定の見直し(ビットレートや解像度の最適化)
👉 あるイベント会社では、一般回線で配信した際に遅延が3秒以上発生し、視聴者の離脱率が開始10分で40%超に達したという報告もあります。
音声トラブル:声が小さい・雑音・途切れ
ライブ配信で映像よりも視聴者の印象を左右するのが「音声」です。人の話す内容が伝わらない配信は、即座に離脱される原因になります。
主な原因:
- ピンマイクや集音マイクが未接続/故障
- 会場内BGM・反響・ノイズ
- ノートPC内蔵マイクのみでの対応
対策:
- 指向性マイク+ピンマイクの併用
- 外部オーディオインターフェイスによるノイズ除去
- 録音環境の静音化とリハーサルによるチェック
💡特にオンラインセミナー形式では、「聞き取れない」「こもっている」といった声が配信後アンケートの低評価原因の第1位に挙がるケースが多数あります。

ここ大事!
口をどこに向けるかも大事なんだよ!?
質疑応答が盛り上がらない
「双方向性」が求められるライブ配信で、質問が出ずに静まり返ると、登壇者も焦ってしまい、配信全体のテンションが下がってしまいます。
主な原因:
- チャット欄の使い方が周知されていない
- 視聴者側の発言ハードルが高い
- 進行が質問タイミングを確保できていない
対策:
- 匿名で質問できるフォームやツール(Slido、Googleフォーム等)の活用
- モデレーターが適宜質問を読み上げる進行体制
- よくある質問を事前収集して“仕込み”を用意
📊実際に、事前に10件以上の質問候補を準備しておくと、質疑応答の満足度が約1.8倍高まるという社内データを公開している企業もあります。
時間配分がずれる・長時間にわたる
リアルのイベントと異なり、ライブ配信では視聴者が「いつでも離脱できる」ため、だらだらと続く構成は最大の敵です。
主な原因:
- 台本・進行表の未作成
- 各登壇者が時間を守らない
- 想定外のトラブルで押してしまう
対策:
- 全体を20~30分のパートに分ける構成
- 台本・スライドの時間記載、カンペを共有
- 配信ディレクター(進行管理役)を置く
⏱「視聴者の集中力は15分が限界」とされる調査もあり、テンポ良く区切る構成が重要です。

導入前に押さえておきたい“よくある質問”と回答
ライブ配信を社内で導入しようとする際、多くの関係者が「本当に大丈夫か?」という不安を抱えます。ここでは、配信支援会社や企業事例から見えてきた、導入検討時によくある質問とその具体的な回答をFAQ形式で紹介します。社内提案書やプレゼンの一部として引用いただくのもおすすめです。
Q. インターネット回線はどのくらい必要ですか?
**A. 安定したライブ配信には「上り回線速度」が特に重要です。**目安として、以下の回線環境が推奨されます。
- 720p配信:上り10〜20Mbps以上(余裕を持って30Mbps以上)
- フルHD(1080p)配信:上り50Mbps以上
- 会場のネット回線が共用の場合:別途モバイル回線や専用回線を用意するのが理想
💡実際に配信支援会社「名古屋ディスプレイ社」では、最低でも上り30Mbpsの確保を基本としています。
Q. 配信に必要な機材はどこまで揃えるべき?
A. 配信の規模や目的によって異なりますが、最低限必要なのは以下です:
- カメラ(デジタル一眼 or ビデオカメラ)
- キャプチャーボード(PCとカメラを接続)
- マイク(指向性 or ピンマイク)
- 配信PC(CPU:Core i5以上/メモリ16GB推奨)
- スイッチャー(複数画面切替時)
- 照明(室内が暗い場合)
👉 専門知識がない場合は「一式レンタル+現地対応」を提供している外注業者に依頼するのが安心です。

わからないことをわからない人がやっても意味ない。
手っ取り早い方法があるんだから。頼らないと。
Q. 配信中にトラブルが起きたらどう対処する?
A. 事前のリスクヘッジと、当日のリカバリ計画が鍵です。
- トラブル予備案(例:ネット断時は録画に切り替える)を用意すること
- モバイルルーターなど、バックアップ回線を準備
- 配信ソフト(OBSなど)上で音声や画面の簡易ミュート切替を練習しておく
💡実際に、ある企業では映像フリーズ時に「録画に切り替えます」という案内画像を即座に表示して難を逃れた事例もあります。
Q. 視聴者から質問がこないと盛り上がらないのでは?
A. 質問が集まらないのは、環境や仕組みの問題であることが多いです。
- 匿名投稿可能な質問フォーム(GoogleフォームやSlidoなど)を使う
- 事前に“よくある質問”を用意しておくことで、質疑応答を自然に開始可能
- モデレーターがコメント欄を拾って場をつなぐ
📊 ある学校説明会では、事前に10個のFAQを“仕込み”で用意し、参加者からの質問数が2倍に増えたという結果も。
Q. 外注する場合、どこまで任せられるの?
A. 配信支援会社によってサービス範囲が異なりますが、基本的に以下の対応が可能です。
- 機材レンタル(設営・撤収含む)
- 台本作成/タイムスケジュール作成
- 配信スタッフの現場常駐
- アーカイブ用の録画編集
- トラブル対応マニュアル整備
🎥 例えば「NEXT STUDIO」や「LIVEA」などは、中継車レベルのプロ仕様の配信から、小規模な説明会まで柔軟に対応しています。
このように、導入前に寄せられやすい不安や疑問をあらかじめクリアにしておくことで、社内の意思決定は格段にスムーズになります。
まとめと次の一歩
ライブ配信の導入は、一見すると「簡単に始められそう」と思われがちですが、実際には多くの企業が**“よくある失敗”**を経験しています。本記事では、導入を社内で提案する方に向けて、以下の3つの視点で必要な知識と材料をご提供してきました。
振り返り:社内提案に効く3つの視点
- 失敗の傾向とその原因
→ 映像・音声トラブル、進行の崩れ、双方向性の不在など、現場で頻出する課題を具体例付きで紹介。 - 実際の配信事例
→ 回線ミスやマイクトラブルを経験した企業の教訓と、それを乗り越えた改善施策を解説。 - よくある質問と回答(FAQ)
→ 「どんな機材が必要?」「トラブル時は?」など、導入を検討する上で避けられない疑問に明確に回答。
次のステップ:導入を現実に近づけるために
社内でライブ配信の提案を成功させるには、「不安を払拭する材料を先回りして用意する」ことが決め手です。以下のアクションを次の一手としておすすめします。
1. 小規模な“テスト配信”を先に実施する
→ 社内イベントや社内報共有など、小さなテーマで試験配信を行うことで、現場の理解と実感が深まります。
2. 配信シナリオ・台本を作成し、簡易リハーサルを行う
→ 話す順番・役割・時間配分などを文書化して関係者に共有すれば、不安や混乱が大きく減ります。
3. 必要に応じて外部パートナーを検討する
→ 内製にこだわらず、まずはプロの配信会社と相談することで、スムーズかつ高品質な配信を体験可能です。
「ライブ配信=本番一発勝負」ではありません。
だからこそ、事前準備と社内理解が何よりも重要です。この記事が、導入を前向きに進めるきっかけとなれば幸いです。
ライブ配信をしてみたいけど、、、、、
なにから手を付ければいいかわからない、、、
何が必要なの?どこでやればいいの?
やりたいんだけど!!!できない!!!
という方は、私たちにお任せください!
全て解決できます。
詳しくはこちらをクリック↓↓