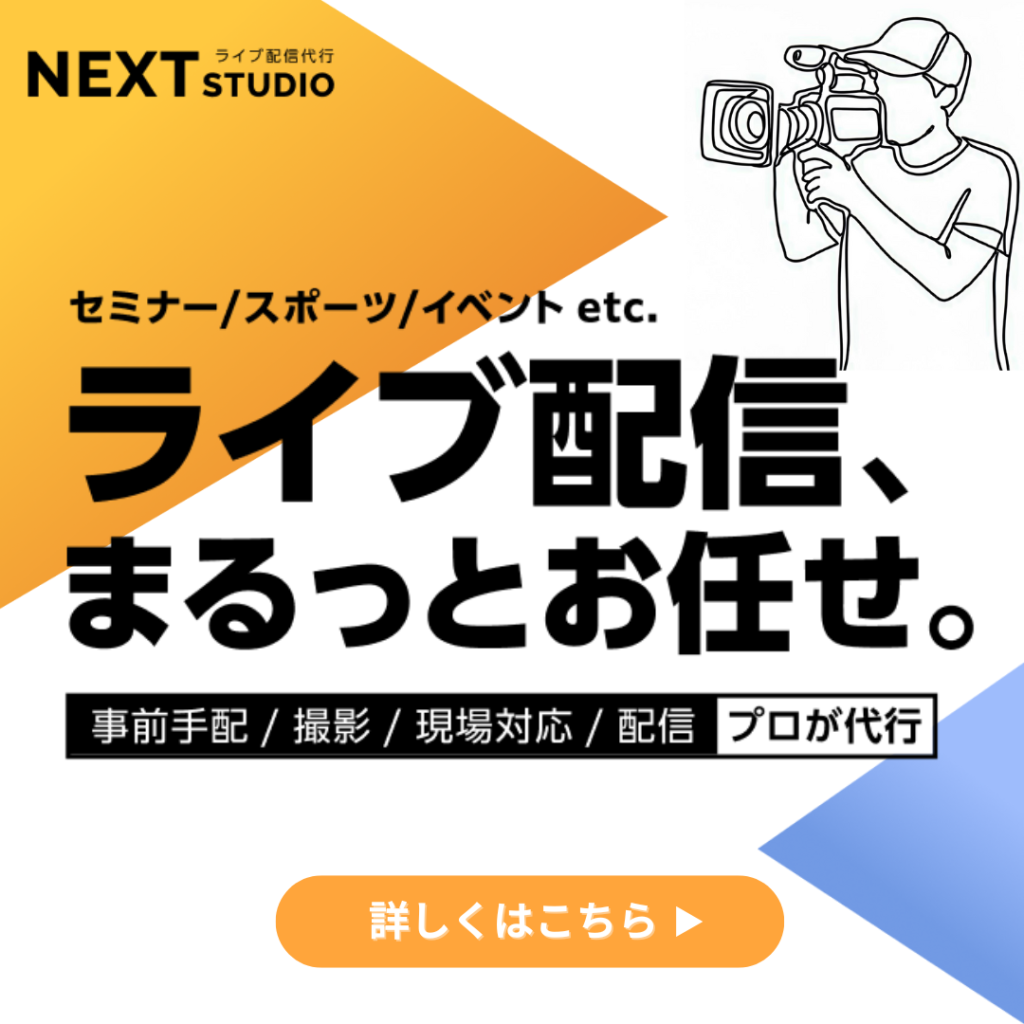ライブ配信の力を、あなたのビジネスに。

コロナ禍を経て一気に普及した「ライブ配信」は、今やエンタメの枠を超え、ビジネスの集客やブランディング、社内コミュニケーションにも不可欠な手段となっています。従来の広告施策では届きにくかった層へのアプローチや、リアルタイムでの顧客エンゲージメント強化など、ライブ配信は多くの可能性を秘めています。
本記事では、ライブ配信を活用してどのようにビジネスに効果をもたらすのか、成功事例を交えながら、集客に結びつける具体的な戦略や実践方法を解説します。これからライブ配信を始めたい方はもちろん、すでに取り組んでいるが成果に悩んでいる方にも役立つ内容をお届けします。
ライブ配信とは?
ライブ配信の定義と役割
「ライブ配信」とは、動画をリアルタイムでインターネット上に配信する技術やサービスを指します。視聴者は、その瞬間に起きている出来事を、離れた場所からでもリアルタイムで視聴できます。
現在、ライブ配信は単なるエンターテインメントを超え、企業が情報を迅速に届けるための有力な手段として位置づけられています。イベント、商品紹介、社内会議、セミナーなど、多様なシーンで活用されています。
リアルタイム配信 vs オンデマンド配信
動画コンテンツは大きく分けて「ライブ配信(リアルタイム)」と「オンデマンド配信(録画)」の2種類があります。
| 配信タイプ | 特徴 |
|---|---|
| ライブ配信 | 今この瞬間を届ける。視聴者との双方向コミュニケーションが可能。緊張感と臨場感がある。 |
| オンデマンド配信 | 収録された動画をいつでも視聴可能。編集済みでクオリティ管理がしやすい。 |
特に視聴者参加型のマーケティング施策においては、ライブ配信が優位に働きます。例えば、チャット機能を用いて視聴者の疑問にその場で答えることで、エンゲージメントを高めることができます。
ライブ配信市場の成長と将来性
日本国内のライブ配信視聴経験者は全インターネットユーザーの多くを占めており、特に若年層を中心にその利用は拡大しています。
また、某研究所の調べによると、2023年度の日本のライブ配信市場規模は約900億円と推定されており、今後もEC連動型のライブコマースや企業向けイベント配信の需要増加により、右肩上がりの成長が予想されています。
ビジネス活用におけるライブ配信の価値
ライブ配信は、企業にとって以下のような価値をもたらします。
- ブランドの透明性を高める:企業の「素顔」をリアルタイムで届けられる
- 双方向の関係構築:コメントやリアクションを通じて視聴者と対話できる
- スピード感ある情報発信:ニュースやプロモーションを即時発信できる
- コストパフォーマンスの高さ:オンライン開催で交通費や会場費を削減
このように、ライブ配信は単なる情報発信を超えて、ファンや顧客との関係性を構築し、売上や認知向上につなげる戦略的な手段になりつつあります。

共に創り上げていく。顧客も一緒になって企業などを
成長させていく。楽しい
ビジネスでのライブ配信活用法
ライブ配信は、あらゆる業種・業態の企業にとって多彩な活用法があります。ここでは特に注目されている3つの主要な活用ケースをご紹介します。
商品・サービスのプロモーション
デモンストレーション配信で「体験」を提供
EC業界やD2Cブランドでは、商品の使用感や性能をリアルに伝える手段としてライブ配信が活用されています。
たとえば、アパレルブランド「ZARA」は自社アプリでライブ配信を行い、リアルタイムでのコーディネート紹介やスタッフとのチャットを通じて、来店体験に近い感覚をオンラインで再現しています。
新製品発表のイベント化
大手企業では新製品の発表会をライブ配信で行うケースが増えています。例えば、某外資系IT企業の製品発表イベントを公式サイトやYouTubeで生配信し、世界中からの注目を集めています。これは一種の「エンタメ化されたPR戦略」であり、企業ブランディングにも高い効果を発揮しています。

世間はエンターテインメントを求め、
それが製品販売のストーリーとなるんだ!
セミナー・ウェビナーの開催
見込み顧客獲得に有効な教育型コンテンツ
BtoB領域では、業界ノウハウや最新トレンドを共有するウェビナーが新規リード獲得の手法として広く浸透しています。某人材支援会社では、営業や人事担当者を対象にした無料ウェビナーを定期開催し、1回の配信で200件以上のリードを獲得したという実績もあります。
このようなセミナー形式の配信は「教育型マーケティング」とも呼ばれ、視聴者の信頼を得ながら商品・サービスへの関心を自然に高める効果があります。
アーカイブ化による資産化
配信後の動画をオンデマンド化しておけば、後日閲覧も可能になります。これは営業資料やFAQの一部として再活用できるため、中長期的な集客資源となります。
社内コミュニケーションの強化
オンライン社内イベントの実施
コロナ禍以降、多くの企業が社内イベントや式典をオンラインで実施するようになりました。
たとえば、三菱ケミカル株式会社では、全国の拠点をつなぐ**「内定式のライブ配信」**を実施。物理的距離を越えて社員同士が一体感を得られる取り組みとして好評でした。実施後のアンケートでは、内定者の満足度が前年比20%以上向上したという報告もあります。
ナレッジ共有や経営メッセージの浸透
リモートワーク環境が一般化する中で、経営陣からのビジョン共有や社内研修をライブで行うことで、全社一丸となった方向性の共有が可能になります。録画と違い、「今この瞬間」に語りかけることにより、社員のエンゲージメントが高まりやすいという特徴があります。
ライブ配信活用のポイントまとめ
| 活用シーン | 主な目的 | 成果イメージ |
|---|---|---|
| プロモーション | 商品理解・購買意欲向上 | 購入率の増加、ファン化 |
| ウェビナー | リード獲得、信頼構築 | 問い合わせ増加、CV向上 |
| 社内コミュニケーション | 組織の一体感、ナレッジ共有 | モチベーション維持、業務効率化 |
ライブ配信の活用範囲は、広告・営業・人事・広報など部門を問わず広がっています。次章では、実際にライブ配信を導入して成果を上げた企業事例を紹介し、より具体的な活用像を描いていきます。
成功事例の紹介
ライブ配信をビジネスに導入し、具体的な成果を上げている企業は増えています。ここでは実際の企業3社による活用事例を取り上げ、それぞれの目的・施策・成果にフォーカスして解説します。

某ソリューション提供会社:展示会のオンライン化で集客力を強化
背景と課題
CAE(Computer Aided Engineering)ソリューションを提供する会社では、かつてはオフラインでの展示会を通じて見込み客との接点を持っていました。しかし、パンデミックを契機に従来の物理イベントが開催困難となり、新たな集客手法としてライブ配信型イベントへのシフトを決断しました。
実施内容
Zoomウェビナーを活用し、製品紹介・業界最新情報・技術デモを盛り込んだ**オンライン展示会**を開催。ブース形式に代わって、複数のテーマ別セッションを連続で配信しました。
成果
- 参加登録者数:約3,000名超
- リード獲得数:通常展示会比で1.6倍
- アンケート回収率:約75%
リアルイベントではリーチできなかった地方企業や中小製造業の参加も増加し、オンラインならではの広域展開のメリットが顕在化しました。
大手化学メーカー:内定式のライブ配信で一体感を醸成
背景と課題
新型コロナウイルスの影響により、例年開催していた新卒内定式が中止となる危機に直面。内定者との信頼関係や企業文化の共有が困難になることを懸念し、オンラインでの内定式実施を検討しました。
実施内容
ライブ配信形式で内定式を開催。代表挨拶、事業紹介、先輩社員との座談会をオンラインで実施し、リアルタイムのチャットや質疑応答を組み合わせました。ZoomとYouTube Liveを併用し、接続の安定性と視聴環境の柔軟性も確保しました。
成果
- 内定者満足度アンケート:前年比+23%向上
- 事後の内定辞退率:前年より20%低下
- 録画アーカイブの再生回数:500回以上
一方的な配信ではなく、内定者参加型の構成にすることで“つながり”を感じやすい工夫が成果に直結しました。
大手運送会社:社内配信によるナレッジ共有と働き方改革
背景と課題
全国に約4万人の社員を抱える佐川急便では、支店間の情報格差やナレッジの共有不足が課題でした。これまでは紙資料やメールでの周知が中心で、現場への浸透に時間がかかる問題を抱えていました。
実施内容
Microsoft StreamやTeamsを活用し、経営層からのビジョン共有、マニュアル紹介、新人研修などを定期的にライブ形式で社内配信。ライブ中の質疑応答や、後日の録画視聴も可能にしました。
成果
- 配信視聴率:全社平均で78%以上
- 業務改善提案数:前年比+30%
- 管理職の現場巡回回数:25%削減
ライブ配信により情報のスピードと一貫性が保たれ、現場の理解度・参加意識が高まる結果となりました。特に現場からのフィードバックでは「経営陣の顔が見えるようになった」「目的が明確になった」といった声が多く寄せられました。
成功企業に共通するポイント
これらの企業に共通する成功要因は次の通りです:
- 目的を明確にし、配信の構成を最適化している
- 視聴者とのインタラクションを積極的に取り入れている
- 録画やアーカイブを通じて、配信後も価値を継続させている
- 使用する配信ツールを目的に合わせて柔軟に選定している
このように、業界・用途を問わず、ライブ配信は**成果につながる「実践的手段」**として多くの企業で機能しています。

発信する形は変われども、それは目的達成のための手段!
目的に向かう姿勢さえ変えなければいい!
ライブ配信の集客戦略
ライブ配信を成功させるためには、**「いかにして視聴者を集めるか」**が極めて重要です。良質なコンテンツを作っても、それが見られなければ意味がありません。ここでは、効果的な集客につながる4つの戦略について解説します。
事前告知の徹底
SNS・メルマガ・LPを組み合わせた多角的アプローチ
ライブ配信の告知は、配信当日から逆算して2週間前〜3日前までに段階的に行うのが理想です。効果的な媒体には以下のようなものがあります:
- X(旧Twitter)やInstagram:短文+画像で拡散力が高い。リマインダー投稿も有効。
- メルマガ:既存の顧客や見込みリストに直接訴求可能。申込フォーム付きが望ましい。
- LINE公式アカウント:開封率が非常に高く、配信直前のリマインダーに最適。
- 特設ランディングページ:配信の目的・内容・視聴方法を集約して伝えるページ。
ある調査によると、**ライブ配信視聴者のうち70%以上が「事前告知によって配信を知った」**というデータもあります。
告知回数の目安
| 配信2週間前 | ティザー投稿・配信日程発表 |
|---|---|
| 配信3〜5日前 | 本番内容の詳細・出演者紹介 |
| 配信当日 | 最終リマインド・URL再告知 |
タイトルとサムネイルの工夫
「見たい」と思わせる入口作りが鍵
↓ここ大事!!!!!!!!!!
ライブ配信のタイトルとサムネイルは、視聴者が最初に接触する要素です。これらが魅力的でなければ、内容がいくら良くてもクリックされません。
タイトル作成のポイント
- 【数字を使う】:例)「5分でわかる〇〇の裏側」
- 【問題提起・疑問形】:例)「なぜ今、ライブ配信が売上を変えるのか?」
- 【ベネフィット提示】:例)「たった1回の配信でリードが2倍に」
サムネイル作成のポイント
- 人の顔や表情を入れる(親しみ・信頼感アップ)
- 大きなフォントで要点を表示
- ブランドカラーを活用し一目で分かるデザインに
YouTube Liveなどでは、サムネイルのクリック率が視聴数に直結するため、時間をかけてでも作り込む価値があります。
配信時間とスケジュールの最適化
視聴者の生活リズムに合わせる
配信時間は、ターゲットとする視聴者層の行動パターンに合わせることが集客効率を高める鍵です。
| ターゲット層 | 最適な配信時間帯 |
|---|---|
| BtoC(一般消費者) | 平日夜(20〜22時)、休日午後(14〜17時) |
| BtoB(法人担当者) | 平日昼休み(12〜13時)、夕方(16〜18時) |
また、**配信を定例化する(例:毎週水曜夜はライブ配信)**ことで、リピーターがつきやすくなります。
リアルタイムのエンゲージメント施策
視聴者参加型の構成で滞在時間を伸ばす
ライブ配信では、「ただ見る」だけでなく、視聴者が参加できる仕組みを用意することで、視聴時間や満足度を大きく高められます。
- コメント・チャットの拾い上げ:名前を呼んでリアクションするだけでも効果的
- リアルタイム投票:ZoomやYouTubeのアンケート機能で参加を促す
- 特典配布:アンケート回答者にクーポンやPDF資料を提供
視聴者が「自分の意見が反映された」と感じることで、その後のファン化・再視聴率アップにもつながります。
成果の最大化にはPDCAが不可欠
初回から大成功する配信はまれです。毎回の配信後に以下のようなKPIを測定し、改善を繰り返すことが重要です。
- 視聴者数(リアルタイム/アーカイブ)
- 滞在時間・離脱率
- コメント数・参加率
- CV率(申し込み・購入・資料請求など)
Google Analyticsや各配信プラットフォームの分析ツールを活用して、次回配信への改善点を可視化しましょう。
ライブ配信に必要な機材とプラットフォーム選び
ライブ配信の成功には、コンテンツの質だけでなく、配信環境の安定性と視聴体験のクオリティが大きく関係します。ここでは、配信を円滑に行うために必要な機材と、それぞれの用途に応じた配信プラットフォームの選定基準について解説します。
必要な機材の基本セット
1. カメラ
- PC内蔵Webカメラ:手軽に始めるには十分だが、画質は限定的
- 外付けWebカメラ(Logitech C920等):フルHD対応で映像クオリティが向上
- 一眼レフ・ミラーレスカメラ:HDMI接続で配信可能。高画質・ボケ感を演出可能
プロフェッショナルな見せ方をしたい場合は、HDMIキャプチャーボード(例:Elgato Cam Link)を使って、一眼カメラをWebカメラ化する方法が有効です。
2. マイク
- USBコンデンサーマイク(Blue Yeti、RODE NT-USB等):クリアな音質でノイズが少ない
- ラベリアマイク(ピンマイク):登壇型や動きの多いシーンに最適
- オーディオインターフェース+XLRマイク:本格的な収録環境に対応
音声の質は視聴者の「離脱率」に直結するため、最低でもUSBマイクは導入すべきといえます。
3. 照明
- リングライトやLEDパネル:顔色や背景の印象が大幅に改善
- 調光・色温度調整が可能なタイプがベスト
自然光が安定しない時間帯や室内での配信では、照明の有無が視聴体験に大きく影響します。
4. 配信用パソコン・回線
- CPU:Intel i5以上、メモリ:8GB以上が推奨
- 有線LAN接続を強く推奨(Wi-Fiは不安定になる可能性あり)
回線速度は最低でも上り10Mbps以上を確保しましょう。Speedtestなどで事前確認が重要です。
配信プラットフォームの選び方
ライブ配信を行う際には、**「誰に届けたいか」「どんな効果を得たいか」**によって、適切なプラットフォームを選ぶ必要があります。
YouTube Live
- 利点:誰でも視聴可能、アーカイブ保存、SEO効果もあり
- 向いている用途:商品紹介、セミナー、カジュアルな配信
さらに、YouTube Liveの活用や配信事例に関心のある方は、こちらのブログ記事「初心者向けYouTubeライブ配信のやり方と注意点を徹底解説】」もぜひご覧ください。
Zoomウェビナー/ミーティング
- 利点:登録制・参加者制限可、資料共有、双方向性が高い
- 向いている用途:BtoBの商談・ウェビナー、社内研修
Microsoft Teams / Google Meet
- 利点:企業向けでセキュリティが高い、業務アプリ連携可
- 向いている用途:社内会議、クローズドな情報共有
Instagram Live / TikTok Live
- 利点:フォロワーへの即時リーチ、コメント反応が活発
- 向いている用途:ブランド認知、個人インフルエンサーとの協業
独自配信システム(Vimeo、J-Streamなど)
- 利点:広告非表示、高度な視聴管理や埋め込み機能
- 向いている用途:企業イベント、大規模セミナー、会員制コンテンツ
配信目的×プラットフォーム選定マトリクス
| 目的 | 最適なプラットフォーム |
|---|---|
| 集客と認知拡大 | YouTube Live、Instagram Live |
| 見込み顧客の獲得 | Zoomウェビナー、Vimeo |
| 社内情報共有 | Microsoft Teams、Google Meet |
| コマース・商品販売 | TikTok Live、ライブコマース専用ツール |
配信を本格的に運用していくなら、**機材の投資と配信基盤の選定は「長期的なコストと成果の分岐点」**になります。
配信ソフト・ツールの選び方
PC配信を行う場合には、配信専用のソフトウェアが必要です。代表的なツールを紹介します。
Wirecast(プロ向け多機能配信ソフト)
- マルチカメラ入力に対応し、映像の切り替えがスムーズに行える
- グラフィックやタイトル、トランジション効果の追加が可能
- ゲストをリモートで呼び込める「リモートゲスト」機能
- ソーシャルメディアとの統合(リアルタイムコメント表示など)
- 対応プラットフォーム:YouTube、Twitch、Facebook Live など
LiveShell X(PC不要の高品質配信デバイス)
- 最大1080/60pの高画質ライブ配信に対応
- 最大3つの配信先への同時配信が可能(マルチストリーミング対応)
- microSDカードへの録画が可能で、アーカイブ用途にも便利
- 本体のみで配信・録画が完結するため、現場の機材を最小限にできる
- 対応プラットフォーム:YouTube、Twitch、Facebook Live など
OBS Studio(無料・高機能・安定性◎)
- オープンソースの人気配信ソフト
- 複数のソース(カメラ、画像、画面共有、音声)を切り替え可能
- シーン設定、テロップ、録画機能なども搭載
- 対応プラットフォーム:YouTube、Twitch、Facebook Liveなど
さらに、OBS Studioについて詳しくまとめたブログ記事「初心者必見!OBSを使ったライブ配信の設定と方法を徹底解説」もぜひご覧ください!
StreamYard(ブラウザ完結型・初心者向け)
- アプリのインストール不要
- 複数人のゲスト出演が簡単に可能
- デザインテンプレートや背景切り替えも豊富
- 無料版では一部機能制限あり
Zoom、Microsoft Teams、Google Meet(セミナー型)
- セミナーや会議、社内配信に適している
- 管理者権限の設定、参加者コントロール機能が豊富
- OBSと併用すれば映像演出も強化可能
ライブ配信の成功ポイントと注意点
ライブ配信は、視聴者との「リアルな接点」を作れる一方で、失敗するとブランドイメージに悪影響を与えるリスクもあります。ここでは、成果につなげるためのポイントと、事前に押さえるべき注意点をまとめました。

ライブ配信成功のためのポイント
視聴者との双方向コミュニケーション
ライブ配信の最大の強みは「リアルタイムの対話性」にあります。視聴者からのコメントや質問にその場で反応することで、次のような効果が生まれます。
- 視聴時間が伸びる
- エンゲージメントが向上
- 信頼感・親近感を得やすい
たとえば、コメントへの反応に名前を添えるだけでも、視聴者は「自分ごと」として捉えるようになります。
コンテンツの構成と時間配分
無計画なライブ配信は離脱を招きます。事前にシナリオやタイムスケジュールを作成し、以下のような構成で設計すると効果的です:
- オープニング(挨拶・趣旨説明)2〜3分
- メイントピック紹介 10〜20分
- 質疑応答・対話パート 10分程度
- クロージング・告知 3〜5分
配信時間の目安は30〜45分程度が理想です。長すぎると集中力が続かず、短すぎると伝えきれません。
配信の定期化
単発配信だけで終わらず、**「定期シリーズ化」**することで、習慣視聴されやすくなります。例:
- 毎週木曜19時は業界トレンド配信
- 月1回の社長トークライブ
これによりチャンネルのファン化→継続的なリード獲得につながります。
トラブルを避けるための注意点
通信環境と機材チェック
配信中の「映像が止まる」「音が出ない」といったトラブルは、視聴者体験を大きく損ないます。以下の点を事前に確認しましょう:
- 有線LAN接続、上り速度10Mbps以上の回線
- 音声・映像の事前テスト(30分前にはスタンバイ)
- バックアップPCやマイクの準備
事前にリハーサル配信を行うことで、現場の安心感も格段に高まります。
著作権・肖像権への配慮
BGMや画像、映像素材の使用には十分な注意が必要です。許諾のないコンテンツを使うと、YouTube等で配信停止やアカウント停止になる可能性もあります。
- 商用利用可の素材サイトを利用(例:Artlist、Pixabay)
- 出演者・登場人物には事前に肖像権同意を取得
ビジネスでの利用だからこそ、法的リスクの管理も必須です。
チャット対応と荒らし対策
視聴者とのやり取りは有効ですが、中には誹謗中傷やスパム的なコメントが投稿される可能性もあります。
- モデレーター(コメント管理者)の配置
- チャット制限機能の活用(YouTubeなら「登録者のみ発言可」設定)
万が一の事態に備え、事前にルールと対応フローを決めておくことが重要です。
ライブ配信は「戦略」と「準備」で決まる
ライブ配信は一見カジュアルに見えても、**視聴者の時間と注意を預かる「本番の場」**です。成功にはコンテンツだけでなく、配信環境・法的配慮・運営体制のすべてが整っている必要があります。
まとめ:ライブ配信をビジネスに活かす未来戦略
ここまでご紹介してきた通り、ライブ配信は今や単なる情報発信ツールではなく、集客・営業・人材育成・ブランド構築に至るまで多面的な効果をもたらす戦略的な手段です。
特にリアルタイムでの視聴者との対話性は、従来の広告やコンテンツでは得られなかった**「即時性」と「感情接点」**を企業にもたらしています。
本記事では、以下のようなポイントを中心に解説しました:
- ライブ配信の基本と市場動向
- ビジネスにおける活用シーンと実例
- 集客のための実践的な施策
- 配信環境とプラットフォームの選び方
- 成功に導くポイントとリスク管理
これらを踏まえると、ライブ配信は「単発の施策」ではなく、事業成長における重要なファネルの一部として捉えることができます。
まずは“小さく始めて、大きく育てる”
ライブ配信は、機材もサービスも以前に比べて導入ハードルが格段に下がっており、小規模なテスト配信からでも始めやすい環境が整っています。
- 社内報告会を社内向けにライブ化してみる
- 小規模ウェビナーで見込み客の反応を確かめてみる
- SNSライブで既存フォロワーと交流してみる
このような「小さな一歩」が、やがて大きな成果へとつながります。
今こそ、ライブ配信を“自社の武器”に
視聴者の目と心を動かすライブ配信は、企業の魅力をそのまま伝えることのできる、極めて人間的なメディアです。そして、そこにはコンテンツだけでなく、企業文化や情熱そのものを届けるチャンスが眠っています。
まだ導入していない企業にとっても、すでに取り組んでいる企業にとっても、今この瞬間が「次のステージ」へのスタートラインです。
あなたのビジネスに、ライブ配信という強力な選択肢を。
我々ネクストアライブはその強力な選択肢になると確信しております。
一緒に企業の価値を高めていきませんか?気になった方は下記画像をクリック!