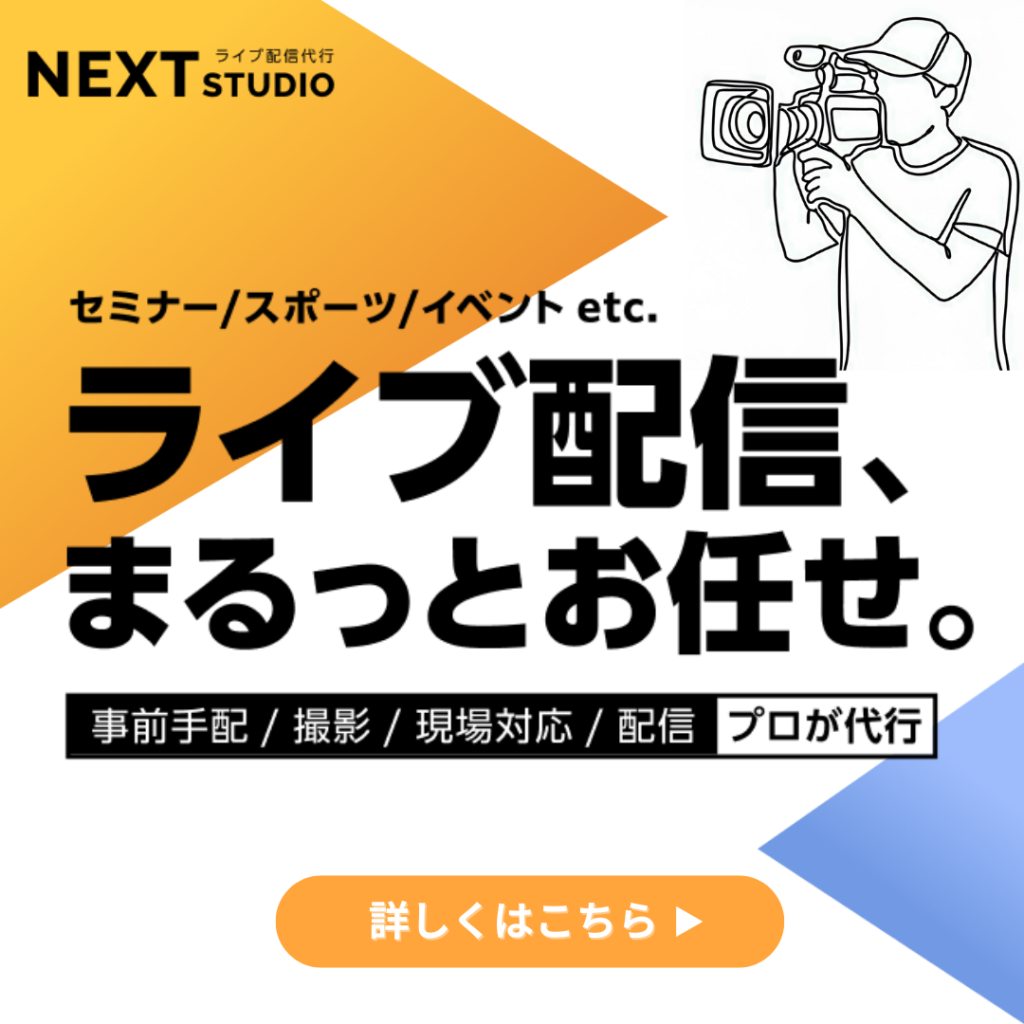はじめに
近年、企業にとって株主との建設的な対話や情報開示の透明性は、IR(投資家向け広報)活動の中核をなす重要なテーマとなっています。とくに新型コロナウイルスの影響を契機として、「対面型一択だった株主総会」にもオンライン対応の波が押し寄せています。
こうした動きの中で注目されているのが「ライブ配信による株主総会の可視化」です。本記事では、IR・総務ご担当者が株主総会のオンライン対応を検討する際に知っておくべき、方式の違い、導入のステップ、メリット・注意点、そして成功している実際の企業事例までを丁寧に解説します。
株主総会について、詳しく知りたい方はこちらのブログ記事「【2025年版】初めての「株主総会とは?」出席の必要性から決議内容、最新事情まで徹底解説」もぜひご覧ください

株主総会のオンライン対応とは?
従来の株主総会は「物理的な会場に株主が集まり、議案説明・質疑応答・議決を行う」というスタイルが一般的でした。しかし、感染症対策や遠方株主の利便性、コーポレートガバナンス強化の観点から、オンライン対応の選択肢が拡大しています。
バーチャル株主総会の方式分類
現在、オンライン対応の株主総会は以下の3つの方式に分類されます。
① バーチャルオンリー型
株主は物理会場に集まらず、完全にオンラインで出席する形式です。日本では2021年の商業登記法改正により、一定の条件を満たす企業がこの方式を選択できるようになりました。
たとえば、某バイオテクノロジー企業は2021年、日本で初めて「バーチャルオンリー型株主総会」を実施した企業の一つです(出席株主は約550名、99.5%が「参加しやすい」と高評価)。
② ハイブリッド参加型
リアル会場に加えて、オンラインでも出席として認められる形式。株主は現地参加もでき、オンラインからも発言・議決権行使が可能です。
③ ハイブリッド視聴型
オンラインでは視聴のみ可能で、出席や議決権行使は不可とする形式。多くの企業が導入しており、ライブ配信を活用する際の主流となっています。
法改正により実現した制度的背景
2021年6月施行の産業競争力強化法改正により、企業は定款を変更することで「株主総会をオンラインで開催する」ことが明確に可能になりました。
また、金融庁や経済産業省からは「株主との対話を重視した形式の工夫」が推奨されており、オンライン方式の拡充が進んでいます。
たとえば、2023年のバーチャル株主総会の実施率は全体の約25%(東京証券取引所調査)に達し、年々その比率は拡大傾向にあります。

ごめんなさい。話を折るようで。
出席すればよくない?どんな形式であれ。
自ら参画することが大事だと思うけどな。
ライブ配信導入のメリット
株主総会のオンライン対応において、ライブ配信の導入は単なる“映像の可視化”にとどまりません。企業にとって、IR戦略やコーポレート・ガバナンスの強化といった観点でも大きなメリットがあります。
参加機会の拡大と情報格差の是正
遠方に住む株主、高齢者、身体的制約のある株主にとって、会場参加は大きな負担となります。ライブ配信により、場所や身体条件に左右されずに株主が参加できる環境が整備され、情報格差の是正にもつながります。
たとえば、あるインフラ企業は2025年6月の定時株主総会において、リアル会場に加えてライブ配信を導入。株主専用サイトでの視聴に対応し、視聴申し込み件数は約5,000件にのぼったと報告されています。
株主との対話強化と透明性の向上
ライブ配信では、総会の進行や質疑応答の様子がそのまま可視化されるため、IR活動の透明性が向上します。加えて、ライブ中のQ&A機能やチャット機能を併用することで、双方向性のあるコミュニケーションも実現可能です。
ある音響機器メーカーでは、ハイブリッド参加型を採用し、株主からのメッセージ投稿も可能な形式で実施。特に2021年以降、対話的な株主総会の実現として評価されています。
危機管理・BCP対策としても有効
地震・台風・感染症など、突発的なリスク要因により対面開催が不可能になるリスクは常に存在します。ライブ配信による株主総会の実施は、こうした緊急時の対応手段=BCP(事業継続計画)の一環として有効です。
実際、2020〜2021年の新型コロナ流行期において、多くの企業が急きょライブ配信に切り替え、法的な開催要件を満たした株主総会を実現しました。

そう。忘れもしないあの時期。
でもあの時期があるから、新しいカタチが出来たんだよね。
ライブ配信導入の課題と対応策
ライブ配信の活用は数多くのメリットがある一方で、技術面・運用面・法制度面において注意すべきポイントも存在します。本セクションでは、よくある課題とその対応策について具体的に解説します。
議決権行使や本人確認の取り扱い
ライブ配信だけでは**「出席」として認められないケースが多い**のが現状です。たとえば「ハイブリッド視聴型」の場合、視聴はできても議決権行使や出席扱いにならないため、事前の議決権行使書面提出などが別途必要です。
対策としては、株主に対して以下を事前に明示しておくことが推奨されます。
- 配信方式(視聴型 or 参加型)
- 議決権の取り扱い方法
- 出席の定義(法的意味合い)
通信・配信トラブルへの備え
インターネット配信には常に**「切断」「遅延」「視聴できない」**といったリスクが伴います。これらのリスクに対処するには、回線冗長化・予備機材の用意・配信事業者との協業が不可欠です。
配信支援企業では、実績に基づいた専用配信サーバーの提供や回線二重化構成を標準化しており、企業はこれらのベンダーと提携することで信頼性を高められます。
セキュリティとプライバシー保護
ライブ配信では、映像・音声・資料がネット上で扱われるため、情報漏洩や第三者による視聴のリスクも考慮しなければなりません。
具体的な対応策としては:
- 株主専用サイト+ログインIDによる視聴制限
- 録画アーカイブの限定公開(オンデマンド配信)
- IP制限や暗号化配信の活用
関西電力のように「専用サイトでのID入力式視聴+事後視聴不可」という形で限定的な視聴権限を設ける企業が増えています。
社内体制とリハーサル不足
配信当日のトラブルや進行ミスの多くは、社内の運営体制や準備不足に起因します。
とくに、ライブ配信に不慣れな場合、役員・議長・進行担当が「カメラ前でどう振る舞うか」に戸惑うことが多く、事前の**模擬リハーサル(最低1回以上)**が効果的です。

導入事例で見る成功ポイント
ここでは、実際に株主総会にライブ配信を取り入れた企業の事例から、成功につながるポイントを探っていきます。IRや総務担当が導入を検討する際のリアルな参考材料として活用ください。
某バイオテクノロジー企業|日本初の「バーチャルオンリー型」株主総会
某バイオテクノロジー企業は、2021年8月に**日本で初めて「バーチャルオンリー型株主総会」**を実施しました。
- 出席株主数:約550名
- 参加満足度:99.5%が「参加しやすかった」と回答
- 出席者は自宅などからPCやスマホで参加し、チャットを通じた質疑応答や投票にも対応
- 法的対応として、定款の変更と総務省への事前届出を済ませたうえで開催
この事例は、「全ての株主が等しく参加できる株主総会」の先駆けとされ、その後の法改正にも大きな影響を与えたと言われています。
某音響機器メーカー|対話重視のハイブリッド参加型
某音響機器メーカーは、2020年から連続してハイブリッド参加型株主総会を実施。
- 視聴だけでなく、株主からの「事前メッセージ投稿」が可能
- 対面参加の人数を制限しつつ、質問はオンラインからも集めて議長が回答
- コメント管理と同時通訳機能も備えたシステムを導入
このように、ただ映像を流すだけではなく、「株主との双方向の対話」を意識した設計が高評価を受けています。
医薬・化学系の上場企業|リアル+配信+オンデマンドの三位一体
医薬・化学系の上場企業は、2023年6月の株主総会でハイブリッド型に加え、オンデマンド配信まで実施する構成を採用。
- リアルタイム配信での視聴者数は前年の1.5倍に増加
- 総会終了後、要点を絞った録画映像をIRページに掲載し、IR活動との連携強化にも貢献
このように、ライブ配信と録画公開を連動させることで、IR全体の発信力を高める戦略が可能になります。
国内インフラ企業|ID認証付きライブ配信の導入
2025年6月、国内インフラ企業は定時株主総会において、リアル会場とライブ配信を併用するハイブリッド視聴型を採用。
- 株主番号・郵便番号によるログイン認証を導入し、視聴対象を限定
- 配信は録画・アーカイブ提供なし、リアルタイム視聴のみに限定
- 議決権行使はオンラインで行わず、書面またはリアル参加が必要
このように、セキュリティと参加制限のバランスをとる配信設計が特徴です。
このような事例からわかるように、目的・社風・株主層に応じた最適な配信設計が、成功のカギとなります。
ライブ配信導入のステップとチェックリスト
ライブ配信付き株主総会を成功させるには、「とりあえず映像を流せばいい」という考え方では不十分です。
配信方式の選定から社内体制の構築、法的手続き、当日運営までを一貫して準備する必要があります。
ここでは、IR・総務担当者が押さえておくべき導入ステップを、チェックリスト形式でご紹介します。
ステップ1:配信方式を決める(参加型 or 視聴型)
- 自社がどのタイプの株主総会を目指すかを決定
└ 株主の議決権行使もオンラインで行う → ハイブリッド「参加型」またはバーチャルオンリー型
└ 配信だけでよい → ハイブリッド「視聴型」 - 定款の確認・変更(バーチャルオンリー型を導入する場合は特に必要)
🟩 チェックポイント
☑ 法的な要件(会社法/金融商品取引法)に合致しているか
☑ 招集通知に開催方法を明記する必要がある
ステップ2:配信業者・プラットフォームの選定
- 安定した配信実績のあるベンダーと提携する
- 対応可能な機能を確認
└ 認証機能/チャット機能/多言語対応/録画配信/画面共有 など
🟩 チェックポイント
☑ 社内での対応か、外部委託かを明確化
☑ 画面構成・UI設計が株主にとって分かりやすいか
ステップ3:セキュリティ・ネットワーク環境の整備
- 配信会場における冗長回線(有線+無線など)の用意
- 万が一のための予備PC/代替配信機材/別回線の準備
- ログイン方式やアクセス制限の確認
🟩 チェックポイント
☑ 自社ネットワークの負荷検証を行ったか
☑ アクセス集中への対応がされているか
ステップ4:株主への告知と案内手続き
- 招集通知・株主サイト・郵送資料にて、ライブ配信の実施方法や視聴方法を丁寧に案内
- ID/PWや株主番号でログインが必要な場合、その案内漏れに注意
- 議決権行使の方法を明示(出席扱いになるか否かも含む)
🟩 チェックポイント
☑ 参加者向けの「よくある質問」を用意しているか
☑ 視聴が困難な株主への代替手段があるか(電話サポート等)
ステップ5:当日の運営と事後対応
- 事前リハーサル(理想的には2回以上)を実施し、社内オペレーションを固める
- 当日はバックアップ対応要員を配置し、現場と配信チームの連携体制を確保
- 配信後、オンデマンド化する場合はIRページへ掲載(場合によっては編集要)
🟩 チェックポイント
☑ リアル会場と配信の進行スクリプトを統合しているか
☑ トラブル発生時のエスカレーションルールを決めているか
このチェックリストをベースに社内での準備体制を整えることで、トラブルの少ない株主総会配信が実現できます。
よくある質問と注意点
ライブ配信付き株主総会の準備を進めるうえで、法的なグレーゾーンや技術的な不安要素について多くの質問が寄せられます。以下に、代表的なFAQとその対処法を紹介します。
Q1:ライブ配信視聴だけで「出席」扱いになりますか?
→ いいえ。配信方式によります。
- ハイブリッド視聴型では、視聴のみで出席とは認められません(議決権も行使不可)
- ハイブリッド参加型またはバーチャルオンリー型において、所定のログイン・本人確認手続きが完了していれば、「出席」扱いになります
補足:出席の可否は、会社法に基づく議決権の行使と関係するため、事前に「総会方式」と「議決権行使の方法」を明示しておくことが重要です。
Q2:視聴できなかった株主からクレームが来た場合はどうすれば?
→ 事前と事後のフォロー体制が重要です。
- 配信トラブル時の連絡窓口(電話サポート)を設置
- 後日、オンデマンド配信(録画)や議事録の送付でフォロー
- 配信支援ベンダーを使えば、専用視聴ページにログイン履歴が残るため、対応履歴として活用可能
Q3:代理人や第三者による不正視聴を防げますか?
→ 一定の防止策は可能です。
- 視聴には「株主番号+郵便番号」や「専用ログインID」の入力を必須にする
- IPアドレス制限・多重ログイン制限・セッションタイムアウト設定の導入
- 機密性の高い内容を含む場合は「オンデマンド配信不可」などの設計にすることも有効です
参考事例:関西電力では「ID入力によるリアルタイム配信+録画提供なし」という形式で、情報漏洩リスクを最小限に抑えた運用を行っています。
Q4:議長や役員がオンライン対応に不安を感じています
→ 事前の模擬リハーサルを必ず実施しましょう。
- 実際の配信画面・カメラ前での立ち振る舞いを体感してもらう
- 通常の進行台本とは別に、**ライブ配信用の「演出スクリプト」**を用意すると安心
- サポート企業では、**現場ディレクター付きの「リハ付き配信プラン」**も提供されています
まとめと検討のポイント
株主総会におけるライブ配信の導入は、IR戦略の高度化や株主との公平な対話の実現において、非常に有効な手段となりつつあります。
ポイントは「映像を流す」ことではなく、株主にとって安心・公平・有益な参加体験をどう設計するかです。
- **方式選定(視聴型/参加型/バーチャルオンリー)**に応じて、法的対応や議決権の取り扱いが異なる
- セキュリティ、通信、当日運営などの技術的な課題は、信頼できる配信事業者との連携でカバー可能
- ユーグレナ、フォスター電機、日本化薬、関西電力などの実例に学ぶことで、より精度の高い導入が可能
今後のコーポレートガバナンス強化、そして企業の信頼性向上のために、ライブ配信という手段を「単なる映像中継」に終わらせず、戦略的な株主コミュニケーションの一環として活用していくことが重要です。
株主総会でのライブ配信に興味がある!という方は下記画像をクリック!
お気軽にお問い合わせください。
楽しく!我々と創造的なライブ配信をしてみませんか?