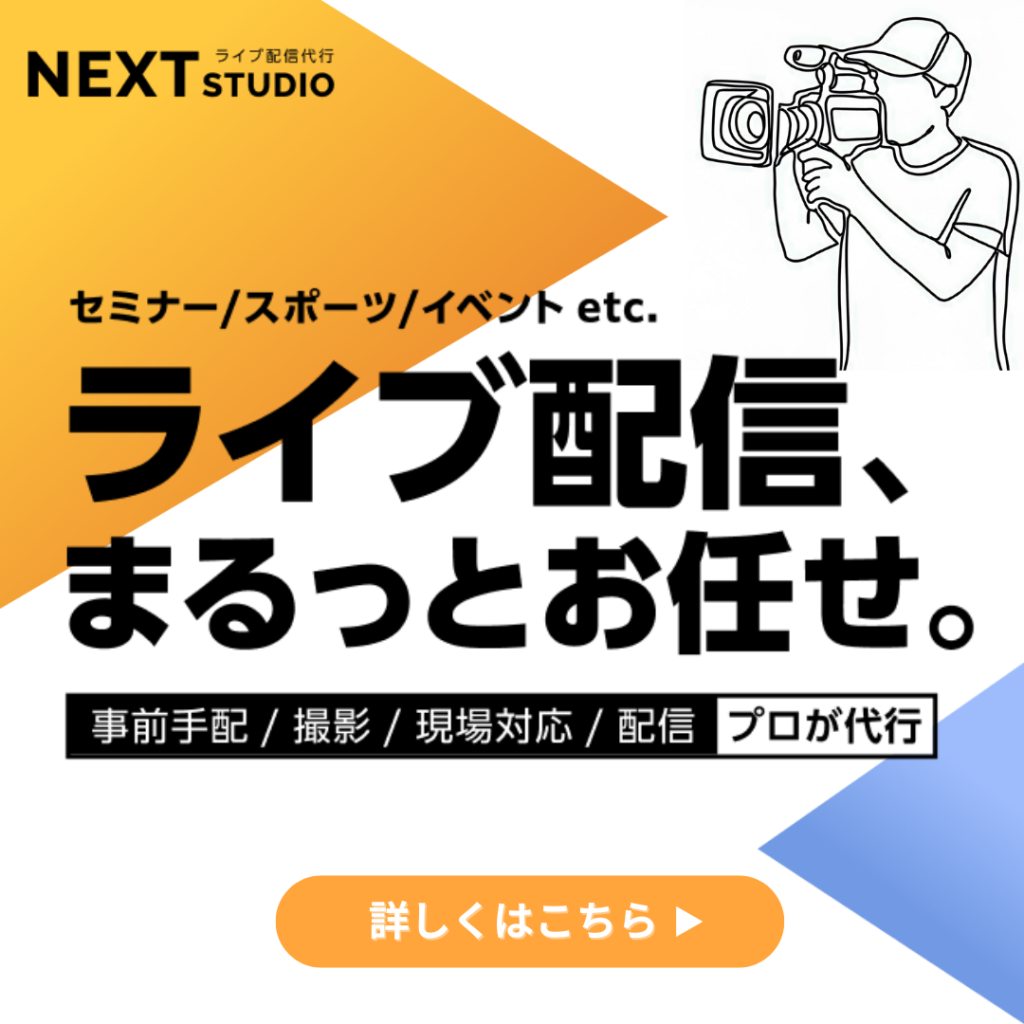はじめに
近年、株主総会のオンライン化が急速に進んでいます。とくに新型コロナウイルスの影響を受け、企業は「集まる」ことのリスクを回避しながら、株主との信頼関係を維持する新たな方法を模索してきました。こうした流れの中で注目されているのが、株主総会のライブ配信です。
本記事では、従来のリアル開催とライブ配信形式を比較し、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。自社に最適な株主総会の形を見つけたいとお考えの企業担当者の方にとって、判断材料となる情報を提供します。
株主総会について、詳しく知りたい方はこちらのブログ記事「【2025年版】初めての「株主総会とは?」出席の必要性から決議内容、最新事情まで徹底解説」もぜひご覧ください

なぜ今、株主総会のライブ配信が注目されているのか
株主総会は、株主との対話や企業の透明性を高めるための極めて重要なイベントです。日本国内では毎年6月を中心に開催され、2024年には約2,000社が6月末までに株主総会を実施したとされています。
ここ数年で特に注目されているのが「ライブ配信を活用した株主総会」です。背景には以下のような複数の要因があります。
- 感染症対策の必要性(コロナ禍)
- デジタル化の加速
- 遠方や高齢株主の参加ハードルを下げたいというニーズ
- ESGやガバナンス重視の風潮
さらに、2021年6月には会社法が改正され、「バーチャルオンリー株主総会」も一定の条件下で可能になりました。これにより、リアル開催に限定しない柔軟な運営方法が制度上でも認められるようになっています。
今や「会場に集まることが当たり前」という考え方は見直されつつあり、企業の規模を問わずライブ配信やオンライン形式を取り入れる企業が増加中です。総会の価値を損なうことなく、より多くの株主へ情報を届ける手段として、ライブ配信は選ばれる存在となっています。

会社に関する決定事項や意見は、現場にいて熱量やニュアンスがわかる。
けども、その熱量は画面からでも伝わるよね?
リアル開催 vs ライブ配信|メリット・デメリット比較
株主総会の形式を選定するうえで、多くの企業が直面するのが「リアル開催とライブ配信のどちらが自社にとって最適か?」という問いです。それぞれに明確なメリット・デメリットが存在し、企業規模や株主構成、開催目的によって最適解は異なります。
ここでは、それぞれの形式の特徴を比較しながら、判断のためのポイントを整理していきます。
【リアル開催】のメリット
- 直接的な信頼構築
経営者が株主の前で説明することで、信頼感や誠意がより強く伝わります。とくに議案に関する丁寧な説明が求められる年には有効です。 - その場の空気感を活かした対応
会場の雰囲気や質問者の様子を踏まえた、臨機応変な進行や対応が可能です。 - 視覚的な演出が可能
資料の展示や製品紹介コーナーなど、企業価値を“体感”できる仕掛けがしやすく、ブランド訴求力も高まります。
【リアル開催】のデメリット
- コスト負担が大きい
会場使用料、交通費、会場スタッフや警備、資料の印刷・配布など、多くの費用が発生します。大企業であれば数百万円以上の費用がかかる場合もあります。 - 参加のハードルが高い
遠方の株主、高齢者、障がいのある方にとっては移動負担が大きく、参加率に影響する可能性があります。 - 感染症や災害などのリスクに弱い
パンデミックや台風等のリスクを考慮しなければならず、中止や延期の判断を迫られるケースもあります。
【ライブ配信】のメリット
- 参加率の向上
全国どこからでも参加可能となり、結果として参加母数が増加。freee社のように参加率1.5倍に増加した例もあります。 - コストの抑制
会場費や人件費が最小限に抑えられ、配信設備・スタッフにコストを集中できる。 - 質疑応答の効率化
質問の事前回収やチャット投稿により、議論の質が平準化しやすい。 - ガバナンス強化につながる
配信内容がアーカイブ化されることで、後日株主やステークホルダーが確認しやすくなり、透明性の向上にも寄与します。
【ライブ配信】のデメリット
- 双方向性に課題がある
視聴者とのコミュニケーションは一方通行になりがち。チャットや質疑対応の工夫が求められます。 - トラブル対応の難しさ
配信中の回線トラブル、映像・音声の乱れなどがあると、信頼性を損なうリスクも。冗長構成やバックアップ体制が必要です。 - 本人確認・議決権行使の技術的課題
システム導入やセキュリティ対策が万全でないと、議決の公正性が問われる可能性もあります。
リアル開催は「深い信頼の獲得」や「企業価値の体験」を重視する場面に向いており、ライブ配信は「効率性」や「アクセスの公平性」を重視する企業にフィットします。
-1-1024x579.jpg)
ライブ配信を取り入れた「ハイブリッド型」が注目される理由
リアル開催とライブ配信、それぞれのメリットを活かし、デメリットを補完する形で近年注目されているのが「ハイブリッド型株主総会」です。これは、リアル会場を設けつつ、同時にオンラインでも配信を行う運営スタイルです。
ハイブリッド型の主なメリット
- 多様な株主に対応できる
高齢者や遠隔地在住の株主、海外投資家まで、物理的・心理的なハードルを下げ、参加機会の平等性を確保できます。 - トラブルリスクの分散
リアル会場にトラブルがあっても、オンライン配信で最低限の開催が可能。逆も然りです。 - ガバナンスと透明性の両立
実際の会場での発言・態度はリアルで伝えつつ、その様子を録画・アーカイブしておくことで、後日株主・メディア・社会全体に向けて公開できます。
導入事例:KDDIや楽天グループ
たとえばKDDIでは、リアル会場での質疑応答に加え、オンライン参加者からの事前質問も受け付ける形でハイブリッド運用を実施しています。楽天グループもリアル開催をベースにしながら、ライブ配信で全国の株主にアクセス可能な体制を構築しています。
これらの事例は、株主との信頼関係を損なわずに効率化を実現した成功例として、今後のモデルケースとなるでしょう。

そう!!大事なのは、どちらかに偏らすのではなく、
両方のいいところを出せる仕組みを作ること!!
まとめと導入検討のポイント
株主総会の形式は、もはや「リアル一択」ではありません。ライブ配信やハイブリッド型の活用によって、より多くの株主に情報を届けられる時代になっています。利便性・コスト・信頼性・ガバナンス強化といった視点から、自社に最適な開催方法を選ぶことが重要です。
とくに参加率の向上やガバナンス意識の高まりを重視する企業にとって、ライブ配信の導入は単なる手段ではなく、企業姿勢を示す戦略的な選択肢となり得ます。
導入にあたっては、セキュリティや運用体制、配信クオリティの担保が必要となるため、専門の業者との連携やガイドラインの整備を検討するとよいでしょう。
株主総会でのライブ配信に興味がある!という方は下記画像をクリック!
お気軽にお問い合わせください。
楽しく!我々と創造的なライブ配信をしてみませんか?