はじめに
近年、「デジタルアーカイブ」という言葉を耳にする機会が増えてきました。自治体や博物館、大学、企業などが、過去に蓄積した資料・写真・映像・記録をデジタル化し、保存・共有・活用する動きが加速しています。
しかし一方で、「デジタルアーカイブにはどんなメリットがあるの?」「課題や注意点もあるのでは?」と、導入を迷う声も少なくありません。
この記事では、デジタルアーカイブの基本概念から実際の活用事例、そしてメリット・デメリットの比較までを徹底的に解説。これから導入を検討する企業・教育機関・自治体のご担当者に向けて、判断材料として役立つ情報をわかりやすくまとめています。
デジタルアーカイブについて、詳しく知りたい方はこちらのブログ記事「【初心者向け】デジタルアーカイブとは?定義・意義・最新事例まとめ」もぜひご覧ください。

実際の活用事例:国内の代表的な取り組み
国立国会図書館デジタルコレクション
日本で最大級のデジタルアーカイブプロジェクトが、国立国会図書館デジタルコレクションです。ここでは、明治期以降の図書・雑誌・古典籍・地図・行政資料などが100万点以上公開されており、誰でもオンラインで閲覧可能です。
✅ 2023年時点での収録点数: 約410万点(うち公開対象は約150万点)
出典:国立国会図書館
研究者だけでなく、学生や一般市民にも開かれた知識の宝庫として活用されています。
地方自治体:東大阪市の事例
東大阪市では、市の広報誌や行政記録をPDF形式でアーカイブし、住民がWeb上から自由に閲覧できるようにしています。これにより、行政の透明性や市民サービスの向上が図られており、他自治体からの注目も集まっています。
このように、デジタルアーカイブは単なる「データの保存」にとどまらず、未来への資産継承・教育・防災・業務効率化など、複合的な意義を持つ技術として各方面で活用が進んでいます。

戦後80年。これを聞いて、時間の長さに目を取られた人。危機感を持ちましょう。
あの頃を伝える人がもういなくなってしまうんです。
当時0歳だった人が80歳。でも、伝えられますか?だから残すんです。
デジタルアーカイブのメリット
デジタルアーカイブの導入には多くの利点があります。単に「紙を電子化する」という作業にとどまらず、情報資産の価値を最大限に引き出す手段として注目されています。以下では、代表的な4つのメリットを具体例を交えて紹介します。
情報資産の長期保存が可能
紙やフィルム、磁気テープなどの物理メディアは、経年劣化や災害によって破損・消失するリスクがあります。国立公文書館の報告によると、紙資料は保管環境が悪ければ20年〜30年で劣化が進行するとされており、永続的な保存には限界があります。
その点、デジタルアーカイブでは、高解像度スキャンやクラウド保存を活用することで、劣化しない形式での長期保存が可能です。バックアップや複製も容易なため、災害や事故による「一括消失リスク」も回避できます。
検索性・アクセス性の向上
デジタル化された情報は、メタデータや全文検索機能によって瞬時に目的の資料へアクセスできます。たとえば、ある企業の広報資料を検索する際、年別・テーマ別に分類されたPDF資料の中から、キーワードを入力するだけで該当ページにジャンプできる仕組みも一般的です。
東京都写真美術館のアーカイブでは、写真作品に撮影年・作家名・被写体ジャンルなどの詳細なタグ情報を付与し、直感的な検索体験を提供しています。これにより、膨大な情報の中から目的の資料をすぐに見つけ出すことが可能です。
業務効率化と活用の幅の広がり
デジタルアーカイブは、保管だけでなく「再活用」を見据えたツールとしても活躍します。たとえば、教育機関では講義録や研究資料をオンライン化し、学生や他大学との共有を促進。企業では過去の広告・製品資料をマーケティング施策やブランド構築に活用しています。
事例として、花王株式会社では広告ポスターや商品デザインの履歴を社内アーカイブ化し、ブランド資産の一元管理とともに、新商品の企画段階でのリファレンスとしても活用しています。これにより、属人的な知識の継承や企画スピードの向上にも寄与しています。
災害対策(BCP)として有効
日本は地震・台風・水害などの自然災害が多く、物理的な保管場所だけに頼るのはリスクが高いとされています。デジタルアーカイブを導入することで、オフサイトやクラウド上への分散保存が可能となり、万が一の際にも情報資産を保護できます。
実際、熊本地震(2016年)後には、多くの文化施設や行政機関で「災害で一部の紙資料が消失した」という報告が相次ぎました。以降、BCP(事業継続計画)の一環として、デジタルアーカイブの整備が加速しています。
デジタルアーカイブのデメリット
デジタルアーカイブには多くの利点がありますが、導入・運用にあたっては無視できない課題や注意点も存在します。ここでは、実際に現場で直面することの多い4つのデメリットについて解説します。
初期導入コストと運用コストがかかる
最も大きなハードルの一つが、初期投資の高さです。デジタルアーカイブを本格的に始めるには、以下のようなコストがかかります。
- 高性能スキャナー・3Dスキャナーなどの機材
- デジタル化作業の人件費または外注費
- サーバーやクラウドストレージの費用
- 専用ソフトウェア・CMSの導入費用
たとえば、3Dアーカイブに使われる業務用スキャナーは1台あたり数十万円〜数百万円かかることもあります。中小企業や地方の博物館・資料館では、こうしたコストが導入のネックになるケースが多いです。
また、初期費用だけでなく、保守・アップデート・セキュリティ対応などの運用費も継続的に必要になります。
著作権・肖像権の処理が煩雑
アーカイブ対象となる資料の中には、第三者の著作物や個人の肖像が含まれる場合があります。これらを無断でデジタル化・公開することは、著作権法や肖像権の侵害となる可能性があります。
特に歴史的な写真・映像には、権利者が不明な「孤児作品(オーファンワークス)」も多く、活用できるかどうかの判断が難しいケースもあります。
実際、地方自治体がデジタルアーカイブを整備する際に、**「権利確認が取れず公開を断念」**するケースが一定数存在します。
メタデータ整備・管理の手間がかかる
デジタル化されたデータには、検索性を高めるための**メタデータ(付加情報)**の整備が欠かせません。たとえば、タイトル・作成者・撮影日・カテゴリなどを1件ずつ手作業で入力する必要があります。
この作業は想像以上に手間がかかり、スタッフの専門知識や業務設計も求められます。メタデータが不正確だと、「検索しても目的の資料が見つからない」「重複・混乱が生じる」といった問題が発生します。
とくに数千件・数万件規模のアーカイブでは、作業量・確認作業・品質管理が大きな負担になるため、体制づくりが重要です。
セキュリティや保存リスクもゼロではない
「デジタル化すれば安心」というわけではありません。サーバー障害、人的ミス、ランサムウェア攻撃など、データを脅かすリスクも存在します。
実際、2021年にはある地方公共団体がランサムウェアの被害を受け、保存していたアーカイブデータの一部が暗号化されてしまった事例も報告されています。
このようなリスクに備えるためには、以下のような対策が求められます。
- バックアップ体制の構築(多拠点・異なるメディア)
- セキュリティソフト・アクセス管理の導入
- 定期的な点検・リカバリ訓練の実施
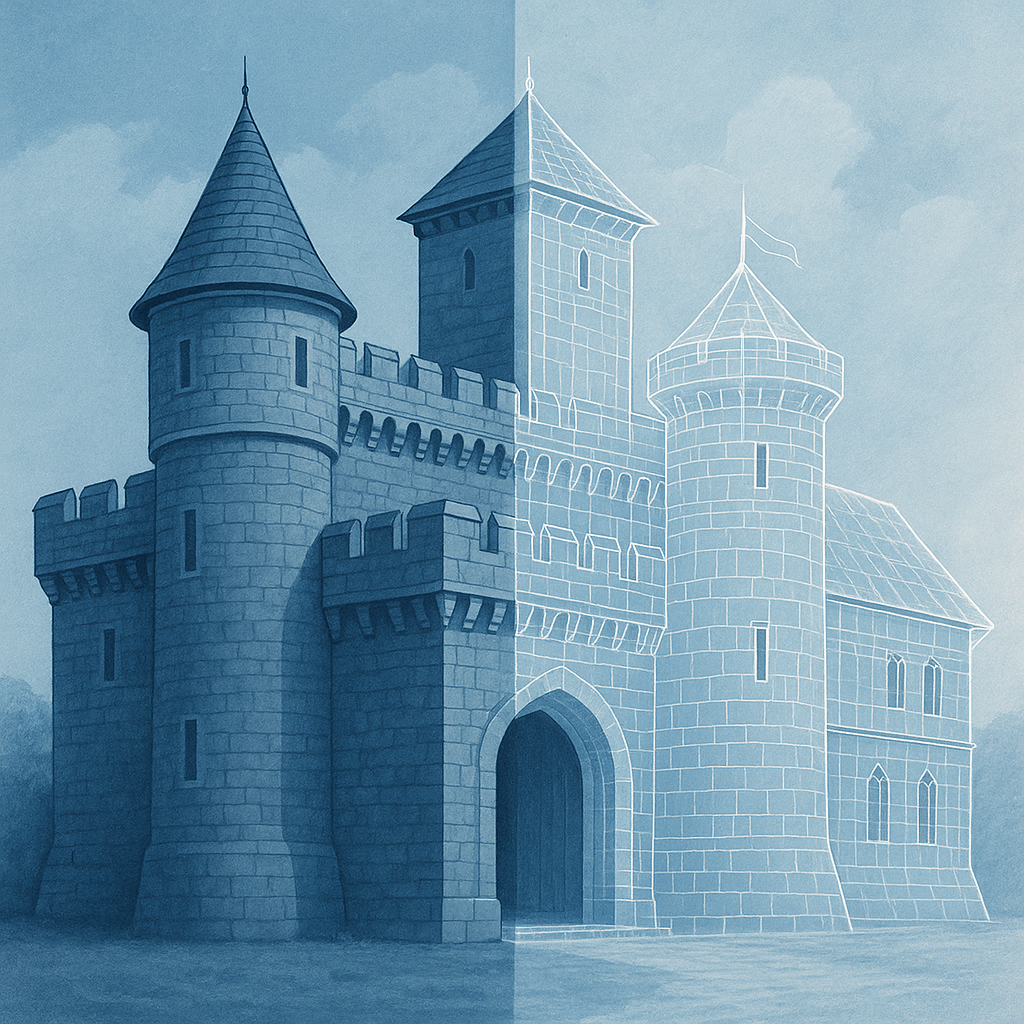
導入前に考えるべきポイント
デジタルアーカイブは多くのメリットをもたらす一方で、導入後に「こんなはずじゃなかった」とならないために、導入前に検討すべき項目があります。
何を、どこまでアーカイブするのか?
まず明確にすべきは、アーカイブの対象範囲と優先順位です。たとえば、すべての紙資料を対象にするのか、特定年以前のものだけか、社外公開するかなど、スコープをあらかじめ決めておくことで、コストや工数の見通しが立てやすくなります。
自社の目的に合ったツールや業者の選定
業種や規模、運用体制によって、適したシステムやサービスは異なります。小規模な企業や自治体であれば、クラウド型サービスや外部委託によって効率的に運用できる場合もあります。
また、社内での検索・共有が目的か、対外的な公開が目的かによっても最適なプラットフォームは変わります。
補助金や助成制度の活用も視野に
自治体・教育機関・中小企業を対象としたデジタル化支援の補助金制度が用意されていることもあります。文化庁や経済産業省、地域の商工会などが提供している制度を事前に調べ、コスト負担の軽減に役立てることも可能です。

やらなければ、お金もかからない。何も起きない。
やれば、お金はかかる。でも、誰かがそれをみて、何か行動を起こせる。
であれば、行動する・しない、どっちをとりますか?
まとめ
デジタルアーカイブは、単なる「紙の電子化」にとどまらず、情報資産の保存・活用・継承という観点から、企業・自治体・教育機関にとって欠かせない取り組みになりつつあります。
本記事では、デジタルアーカイブの**メリット(保存性・検索性・業務活用・BCP)**と、**デメリット(コスト・権利処理・手間・セキュリティ)**を比較し、導入前に検討すべき要素についても解説しました。
重要なのは、自社にとって「何のためにアーカイブするのか」という目的を明確にし、無理のない範囲から一歩ずつ進めることです。将来の価値を守るために、今こそアーカイブの一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
株式会社ネクストアライブでは、最新の360°3D VRカメラを活用したウォークスルー閲覧サービス「next360」 を提供しています。施設や空間を高精細な360°4K映像で記録し、まるで現地を歩いているかのような体験をPC、スマートフォンのブラウザで閲覧が可能になります。
このようなバーチャル空間は、ただ保存するデジタルアーカイブを超えて、観光施設や学校のバーチャル案内、不動産のオンライン内覧、企業のプロモーションなど、「体験を伝えるメディア」としても大いに活用可能です。
デジタルアーカイブを単に「記録する」だけでなく、「感じさせる・伝える」資産にしたい方は、ぜひ next360 の導入をご検討ください。
ご相談は下記画像をクリックし、問い合わせください!お待ちしております!



で変換されているような画像-150x150.jpg)
