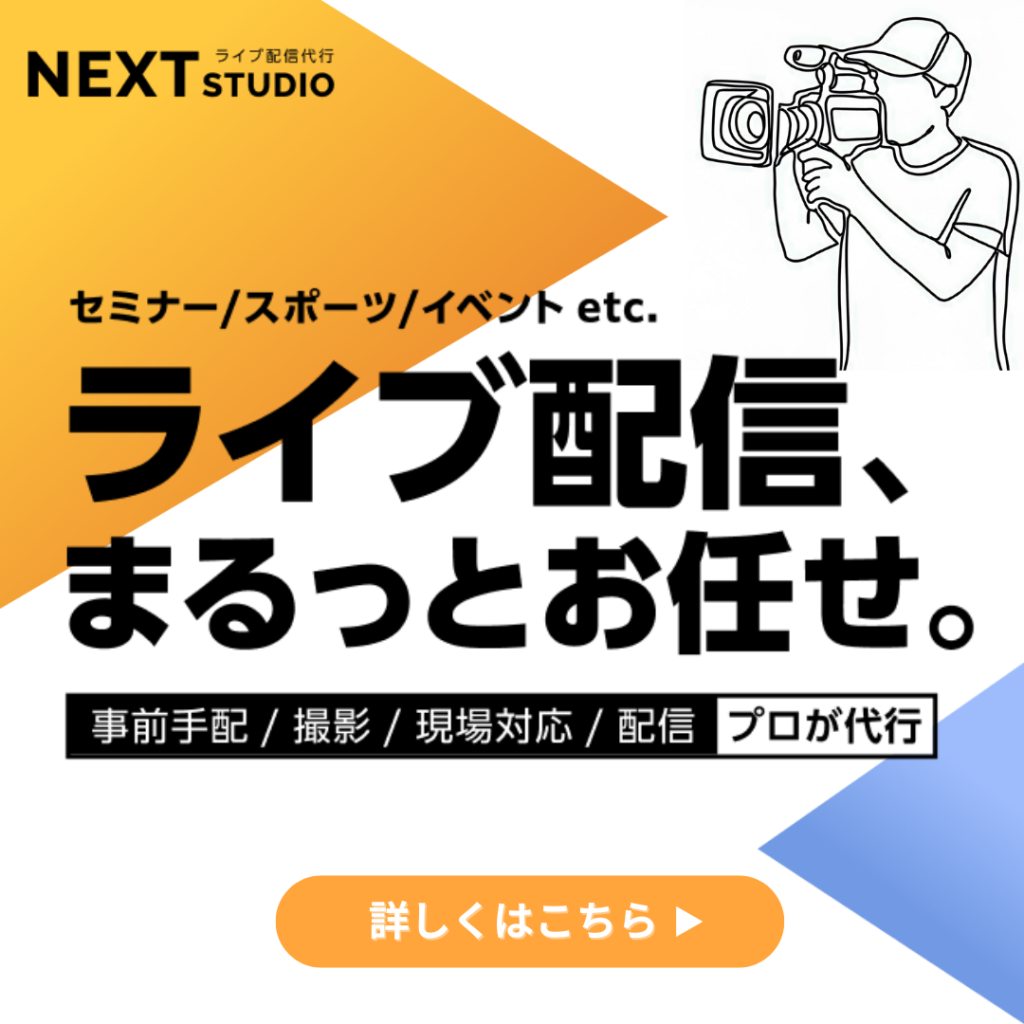はじめに
株式投資を始めて少し慣れてきた頃、「株主総会のご案内」が届いて戸惑った経験はありませんか?
「これ、出席した方がいいの?」「そもそも何をやっているの?」という疑問は、多くの個人投資家が最初に抱く自然な気持ちです。
この記事では、「株主総会とは何か?」という基本から、出席の必要性、実際に何を決めているのか、近年急増しているライブ配信による参加の動きまで、初めての方向けにやさしく解説していきます。

株主総会とは何か?
株主総会とは、株式会社の経営に対して株主が意見を述べ、重要事項を決定するための「最高意思決定機関」です。
会社法に基づき、原則として全ての株式会社において開催が義務づけられています。特に上場企業では毎年1回の「定時株主総会」が行われ、会社の運営方針や配当、役員の選任などが議論されます。
定時株主総会と臨時株主総会の違い
株主総会には主に次の2種類があります。
- 定時株主総会:毎事業年度終了後に開催される、年1回の総会。決算報告や配当、役員選任などが行われます。
- 臨時株主総会:必要に応じて随時開催される総会。M&Aや定款変更など、緊急かつ重大な議案がある場合に開かれます。
たとえば3月決算の企業であれば、6月中旬から下旬にかけて定時株主総会が集中して開かれます。このため、6月は「株主総会シーズン」とも呼ばれます。
出席できるのは誰?株主の基準とは
株主総会に出席できるのは、「基準日」(多くは決算月の末日)時点で株式を保有していた株主に限られます。
たとえば、2025年3月31日が基準日の企業の場合、その日に1株以上を保有していれば、6月の総会に出席する権利があります。基準日以降に売却した場合でも、出席権は残ります。
また、出席には「議決権行使書」の提出が必要であり、直接会場に足を運ばなくても、書面やインターネット経由で議決権を行使することも可能です。
実際に開催されている数
2024年6月期においては、上場企業2,400社以上のうち、約80%が6月中に定時株主総会を開催しました(日本取引所グループの集計データより)。
このうち、ライブ配信などを取り入れたハイブリッド型総会を実施した企業は全体の約40%を超えており、今後も増加が予想されています。
株主総会で何が決まるの?重要事項を整理

株主総会ってなにー?
会社の大事なことを株主が話し合って決める会議だよ。
株主総会では、会社の経営方針に関わる重要な事項が審議・決議されます。
特に上場企業の「定時株主総会」では、以下のようなテーマが主要議案として取り上げられます。
決議される主な事項
株主総会で決められる内容には、大きく次のようなものがあります。
- 取締役や監査役などの選任・解任
経営陣の信任を問う非常に重要な項目です。取締役の任期満了や不祥事があった場合などに選任・解任が行われます。 - 剰余金の配当(株主への利益分配)
1株あたりの配当金や、その実施タイミングについても決議されます。株主にとって非常に関心の高いテーマです。 - 定款の変更
事業内容の追加や、本店所在地の移転など、会社の根幹に関わるルール変更は、株主総会での決議が必要です。 - ストックオプションや株式分割の承認
経営陣や従業員へのインセンティブとしての発行も、株主の同意を得る必要があります。 - 吸収合併・会社分割などの組織再編
M&Aやホールディングス化などの重要な組織変更は、株主総会での決議を経て行われます。
これらの議案は、会社からの招集通知に記載され、事前に確認できるようになっています。
普通決議・特別決議・特殊決議の違い
株主総会の決議には、賛成に必要な株主の割合によって種類が分かれています。
| 決議の種類 | 内容 | 成立条件 |
|---|---|---|
| 普通決議 | 役員の選任・配当など | 出席株主の議決権の過半数の賛成 |
| 特別決議 | 定款変更・合併など | 出席株主の議決権の2/3以上の賛成 |
| 特殊決議 | 会社の解散など重大案件 | より厳しい基準(会社法に規定) |
たとえば、ある企業で「社外取締役の選任」が議題に上がった場合、それは通常「普通決議」で決定されます。一方で、子会社の売却などは「特別決議」が求められ、株主の3分の2以上の賛成がなければ通りません。
実際の事例:大手情報通信企業の例
2023年6月に行われた大手情報通信企業の株主総会では、以下のような重要事項が議案として提出されました。
- 社外取締役の任命(普通決議)
- 定款の一部変更(特別決議)
- 剰余金の配当額決定(普通決議)
これらの議案はすべて可決されましたが、特に定款変更に関しては一部株主から反対意見も出るなど、活発な質疑が行われたことが報じられています。
このように、株主総会では単に報告を聞くだけでなく、株主が会社の方向性に対して意見を反映させる「投票の場」として機能しているのです。

株主としての参加の意義と出席の必要性
株主総会への出席は、法律上「義務」ではありません。
とはいえ、株主である以上、経営方針に直接関われる数少ない機会でもあり、出席することには大きな意義があります。
出席は必須ではないが、権利として重視される
会社法では、株主総会への出席義務は定められていません。つまり、案内が届いたからといって、必ず出席しなければならないわけではありません。
ただし、総会に出席しない場合でも、以下のような方法で議決権を行使できます。
- 書面による議決権行使(郵送で事前に投票)
- インターネット投票(専用システムから議案に賛否を示す)
- 代理人による出席(信頼できる家族や弁護士などを代理に立てる)
特に近年は、オンラインで手軽に議決権行使ができる企業も増えており、物理的に会場に行くハードルは低くなっています。
「株主提案権」などの権利も行使できる
出席することで、以下のような株主固有の権利を実際に使うことも可能です。
| 権利名 | 内容 | 必要株数の目安 |
|---|---|---|
| 株主提案権 | 総会の議題を提案できる | 発行済株式総数の1%以上(6カ月以上保有) |
| 議案への質問・質疑 | 経営陣へ直接質問できる | 特別な条件なし(出席株主であれば可能) |
| 招集請求権 | 臨時株主総会の開催を請求できる | 発行済株式総数の3%以上(6カ月以上保有) |
このように、議決以外にもさまざまな「意見表明」の機会があるため、積極的に活用することで企業に対して健全なプレッシャーをかけることができます。
個人投資家こそ“顔の見える経営”を体感できる場
とくに個人投資家にとって、株主総会は企業の雰囲気やトップマネジメントの姿勢を直接感じ取る絶好の場です。
- 社長や取締役の発言内容
- 株主の質疑応答のリアルなやり取り
- プレゼン資料や事業報告の熱量
これらはIR資料だけではわからない“空気感”であり、長期投資や追加投資の判断材料として非常に参考になります。
さらに、会場によっては株主向けの記念品(クオカードや食品、自社製品など)が配布されることもあり、ちょっとした楽しみもあります。

株主総会に参加すると、その会社がどんな考えで動いているかを知れたり、
自分の意見(投票)で会社に関われるのがいいところだよ。
将来お金の使い方や会社を見る目を養うチャンスにもなるんだ。
実際の出席方法と流れ
「株主総会に出席してみたいけど、どうすればいいのかわからない」という方のために、ここでは具体的な出席方法や当日の流れについてご紹介します。
株主総会の案内はいつ届く?
総会の約2〜3週間前になると、株主宛に「招集通知」が郵送または電子交付されます。
この招集通知には、以下のような重要情報が記載されています。
- 開催日時・場所(リアル/オンライン)
- 議案の内容(配当・役員選任・定款変更など)
- 議決権行使の方法(書面・オンライン・出席など)
- 株主番号・パスワード(オンライン投票に必要)
最近では、紙の書類だけでなく、**「スマート行使」や「議決権電子行使プラットフォーム(ICJ)」**を利用したオンライン投票にも対応する企業が増えています。
出席の流れと当日の進行
実際に会場に出席する場合、以下のような流れで総会は進行します。
- 受付・本人確認
議決権行使書や本人確認書類を持参して受付を行います。 - 開会・議長挨拶
通常は代表取締役が議長を務め、開会を宣言します。 - 事業報告・決算説明
前年度の業績や今後の事業方針について説明が行われます。 - 議案の提案と質疑応答
議案の説明の後、出席株主からの質問を受け付ける時間が設けられます。 - 議決(投票)
書面または挙手などで議案ごとの賛否を表明し、可決/否決が決まります。 - 閉会
所要時間は1〜2時間程度が一般的です。大規模な企業では3時間を超えることもあります。
過去に行われた実例:某アパレルメーカーでの株主総会
2024年6月に開催された某アパレルメーカーの株主総会は、東京での会場開催+オンライン配信のハイブリッド形式で実施されました。
会場には200人以上の株主が集まり、柳井正会長が業績やグローバル戦略について熱弁をふるい、参加者との質疑応答も活発でした。
事前に議案や想定Q&Aがオンラインで開示されており、投資初心者でも理解しやすい設計だった点が印象的です。

ライブ配信・ハイブリッド株主総会の最近事情
近年、コロナ禍を契機に広がったのが「ハイブリッド型株主総会」や「ライブ配信による参加」です。
物理的に会場へ行けない株主や、遠方在住の個人投資家にとっては、オンラインで参加できる仕組みは大きなメリットとなっています。
ハイブリッド型株主総会とは?
「ハイブリッド型」とは、会場開催とオンライン配信を併用する形態のことを指します。
会社法上は以下の2種類に分類されます。
- ハイブリッド参加型:会場での開催を前提にしつつ、株主はオンラインで“視聴のみ”が可能。
- ハイブリッド出席型:株主がオンラインで“正式出席”扱いとなり、議決権行使や質疑応答にも対応。
2021年から金融庁のガイドライン整備が進み、2023年には東京証券取引所もこれを推進する姿勢を強めたことで、上場企業を中心に導入が加速しました。
実際の導入率と企業の動向
2024年6月期においては、上場企業のうち約45%が何らかのオンライン対応を実施しています。
その内訳は以下の通りです(経済産業省・東京証券取引所の発表より集計)。
- ハイブリッド参加型:約1,000社以上
- ハイブリッド出席型:約300社程度
- 完全バーチャル型(物理会場なし):一部のスタートアップ企業など限定的
特にIT・通信・不動産業界では導入が進んでおり、株主の利便性向上と情報公開の透明性確保という両面のメリットが評価されています。
メリットと課題
メリット:
- 遠方や多忙な株主も参加しやすい
- 会場設営コストの削減(長期的に)
- 多くの株主に経営情報を届けられる
課題:
- 通信トラブルのリスク(接続不良や映像乱れ)
- 本人確認や議決権行使の安全性担保
- 質疑応答の公平性確保
これらをクリアするため、企業側では信頼性の高いライブ配信システムや、ICJのような認証付き議決権行使プラットフォームの導入が進んでいます。
実例:大手製造業のライブ配信活用
2024年6月に実施された大手製造業の定時株主総会では、ハイブリッド出席型が採用され、
オンライン参加者にも議決権行使の権利が与えられました。
社長の永守重信氏が「経営の健全性は株主の声に支えられている」と語る場面が印象的で、双方向の対話型総会の先進事例として注目を集めました。
よくあるQ&A形式で素朴な疑問に回答
ここでは、初めて株主総会に参加する人が抱きがちな疑問を、Q&A形式でまとめてお答えします。
Q. 株主総会に出席しないとどうなるの?
A. 出席しなくても特にペナルティはありません。
ただし、議案に対する自分の意思を示さないことになるため、「投資家としての声」を経営に届ける機会を逃すことになります。
出席できない場合でも、書面やオンラインでの議決権行使を活用しましょう。
Q. 議決権ってどのくらいの力があるの?
A. 1株につき1票の議決権があります。
大株主でなくても、取締役選任や配当に関する重要な議案に賛否を表明することができます。
企業によっては、個人株主の動向が議案可決に影響するケースもあります。
Q. 株主総会のライブ配信って誰でも見られるの?
A. 基本的には「その会社の株主のみ」が視聴可能です。
招集通知に記載されたログイン情報や専用IDが必要なケースが多く、一般公開されることは稀です。
一部の企業では、株主向け説明会やIR動画として編集版を公開する場合もあります。
Q. 議案に反対したいときはどうすれば?
A. 議決権行使書の提出時、またはオンライン投票画面で「反対」を選べばOKです。
出席する場合は、挙手や投票用紙で賛否を示すことになります。
反対票が一定数集まることで、役員案が否決される事例も過去に実際にありました。
Q. 出席したら質問はできるの?
A. はい、会場出席者は質疑応答の時間に手を挙げて質問できます。
オンライン出席型の場合は、事前投稿やチャット形式で質問できる企業もあります(企業によって異なります)。
ただし、発言できる人数には限りがあるため、事前に要点を整理しておくと良いでしょう。
このように、株主総会は「敷居が高そう」と感じていた方でも、意外と身近で参加しやすい場であることがわかります。
まとめ:株主総会は“株主の特権”を実感する場
株主総会は、単なる形式的なイベントではなく、株主が企業の経営に対して直接的に意見を反映できる貴重な機会です。
出席するかどうかは自由ですが、
- 議決権を使って意思表示をする
- 経営陣の説明を聞いて企業の将来性を見極める
- 他の株主の質問を通して多様な視点を得る
といった、「投資判断のヒント」が詰まった場であることは間違いありません。
また、近年はライブ配信による視聴参加や、オンラインでの議決権行使といった手段も整備されつつあり、個人株主にとっても参加しやすい環境が整っています。
株主総会に向けて、まずできること
- 証券会社の口座内で、自分が保有する銘柄の「総会案内」が届いていないかを確認する
- 届いたら、議案の内容や議決権行使の期限をチェック
- 出席できない場合も、スマホやPCからオンライン投票を活用する
「出席=難しいもの」ではありません。
**“株主としての第一歩”**を踏み出すことこそが、長期的な資産形成にもつながります。
株主総会でのライブ配信に興味がある!という方は下記画像をクリック!
お気軽にお問い合わせください。
楽しく!我々と創造的なライブ配信をしてみませんか?