はじめに
かつてメールによるファイル送信の「安全対策」として広まった“PPAP方式”。しかし現在、この方法は「セキュリティリスクの温床」として多くの企業や行政機関が見直しを始めています。2020年には政府がPPAP廃止を宣言し、企業も次々と代替手段へ移行しています。本記事では、なぜ今「脱PPAP」が求められるのか、その背景と理由、安全な代替策までを、最新の事例とデータを交えてわかりやすく解説します。
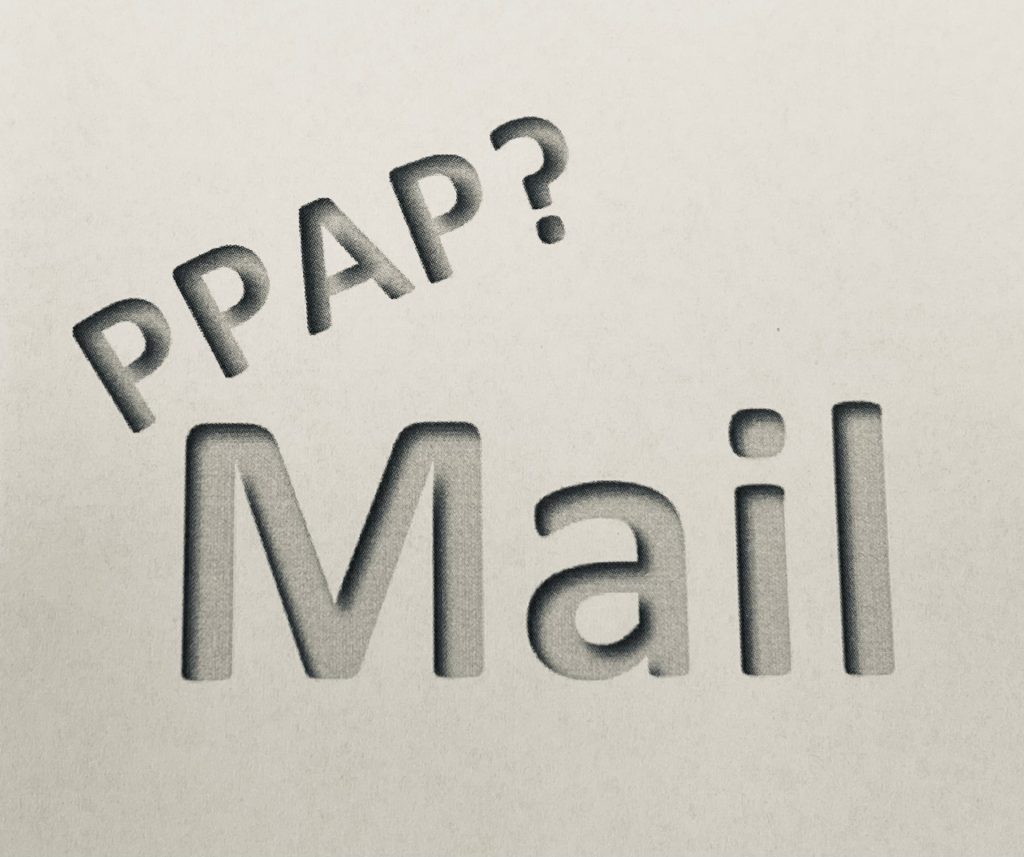
PPAPとは――広まった背景と仕組み
PPAPの手順と目的
PPAPとは、「Password付きZIPファイルを送る→Passwordを別メールで送る」という一連の手順を指します。名前の由来は以下の略称です。
- P:Password付きZIPファイルを送付
- P:Passwordを別メールで送付
- A:暗号化(Archive)
- P:プロトコル
この方法は、日本企業特有の「メール添付文化」のなかで、安全性を高める目的で広まりました。特にファイル転送サービスの導入が進んでいなかった2010年代には、シンプルで無料でできるセキュリティ対策として多くの企業が採用していました。
企業に浸透した経緯
PPAPが広まった背景には、日本企業に特有の「メールは公式な情報伝達手段である」という文化があります。ファイルを添付する際、誤送信や盗聴リスクを少しでも下げるため、パスワード分離が「なんとなく安全」と捉えられ、社内ルール化されました。
特に官公庁では、セキュリティ対策を形として示す必要があったこともあり、PPAP方式が定着。その影響を受けて、取引先とのやり取りにPPAPを強要される中小企業も増えたのです。
しかし、ここ数年で「その安全対策、実は危険では?」という認識が急速に広がりつつあります。
PPAPの何が問題なのか
ZIP暗号の脆弱性と同一経路送信のリスク
PPAP方式の根本的な問題は、「ZIPファイルとパスワードを同じ経路(メール)で送る」という構造にあります。これでは、万が一メールが盗聴・傍受された場合、添付ファイルもパスワードも同時に漏えいしてしまいます。
さらに、ZIP形式の暗号化は非常に弱く、総当たり攻撃(ブルートフォース)や辞書攻撃で比較的簡単に突破されることがわかっています。国際的にもZIP暗号の安全性は保証されておらず、米国国家安全保障局(NSA)や欧州の情報機関も利用を推奨していません。
マルウェア検知がバイパスされる危険性
もう一つの重大な問題は、マルウェア検知のバイパスです。企業のメールゲートウェイには通常、ウイルススキャンが組み込まれていますが、ZIPファイルにパスワードがかかっていると、中身をスキャンすることができません。これを悪用したマルウェア(特に「Emotet」などの標的型攻撃)が増加しており、実際に多数の企業で感染事例が報告されています。
2022年には、ある地方自治体が受け取ったパスワード付きZIPにマルウェアが仕込まれており、庁内ネットワークに深刻な影響を与えた事例もあります。
誤送信対策として不十分
PPAPは誤送信対策としても不完全です。仮に間違った相手にファイルを送ったとしても、パスワードも同じメールアドレス宛に送れば、意味がありません。逆に、パスワードだけ別の手段(例:電話)で伝える運用は現場負荷が高く、形骸化しやすい傾向があります。
業務効率・ユーザー体験の低下
最後に、PPAPは業務効率を著しく下げるという実務的課題もあります。受信者はZIPファイルをダウンロード→解凍→パスワード入力という手間を強いられ、スマートフォンやタブレットではZIPファイルが開けないケースも少なくありません。
取引先や顧客から「面倒」「見られない」「再送してくれ」と言われることも多く、結果として社内外の対応コストがかさんでしまうのです。

危ないことを危ないと見極め、それを自分事に落とし込めるか。
人生において大切なこと!!
なぜ“脱PPAP”が加速しているのか
政府・行政の廃止方針とガイドライン改訂
2020年11月、平井卓也デジタル改革担当大臣(当時)が「内閣府および中央省庁はPPAPを廃止する」と明言したことは、企業にとって大きな転換点でした。その後、すべての府省庁が「ZIPファイル付きメールの受信を拒否」する対応を2021年から順次開始。これは日本国内におけるPPAP廃止の流れを一気に加速させました。
さらに、総務省や経済産業省のセキュリティガイドラインも改訂され、「ZIP暗号メールによる添付ファイル送信は推奨されない」との明記がなされています。
企業側の最新調査:7割が移行段階
2023年には、国内企業の約73.7%が「PPAPの廃止または代替策の検討を進めている」と回答しました(出典:https://www.cybersolutions.co.jp/product/securitysuite/cmss-blog/24242/)
また、すでに完全に廃止済みと回答した企業は約20%。このように、PPAPを続ける企業が“少数派”になりつつある現状がデータからも明らかになっています。
セキュリティインシデント(Emotet 等)の増加事例
2021年〜2022年にかけて流行したマルウェア「Emotet」は、主にパスワード付きZIPファイルを使って感染を拡大しました。被害を受けたのは大企業だけでなく、地方自治体や教育機関、中小企業にも広がっており、復旧コスト・名誉毀損・業務停止といった甚大な損害が発生しました。
こうした事件を通じて、セキュリティ部門だけでなく経営層までもが「PPAPでは守れない」と認識するようになったのです。
法令遵守・取引先の受信拒否という外部圧力
PPAPを続けることのデメリットは、セキュリティリスクだけにとどまりません。取引先の中にはすでに「パスワード付きZIPファイルの受信を拒否」している企業も多く、PPAPを使うことでやり取りそのものができなくなるケースも出てきています。
また、個人情報保護法や改正電子帳簿保存法など、近年の法令強化により、「送受信履歴のログ管理」や「安全なデータ保持」が求められる中、PPAPは適していないという判断が広がっているのです。

卒業式で生徒から、「あの時の先生の言葉がわかりました」
こう言ってもらったときは嬉しかったなー。
成功事例で見る脱PPAPの効果
中央省庁:ZIP暗号化メール受信拒否の徹底
内閣府や各省庁は、2020年末から順次「ZIPファイル付きメールの受信を一律で拒否」する体制に切り替えました。これにより、PPAPを使った添付ファイルの送付が不可能となり、官民間のやり取りでもPPAP廃止が加速しました。
とくに、防衛省や経済産業省はクラウドストレージや共有ポータルを使ったファイル受け渡しに移行しており、添付ファイルの誤送信防止とログ管理を強化しています。
情報通信業:Bizストレージ ファイルシェア導入で工数40%削減
某情報通信業者が提供する法人向けサービス「Bizストレージ ファイルシェア」では、パスワード不要でワンタイムURLを発行し、期限付きで安全にファイル共有が可能です。
同サービスの導入企業では、**「PPAP方式にかかっていたファイル圧縮・パスワード通知・確認連絡の手間がなくなり、関連工数を40%以上削減できた」**という具体的な成果が報告されています
さらに、ワンタイムURLの無効化設定やダウンロード履歴の取得により、情報漏えいリスクの可視化も実現しています。
金融機関:大規模ユーザー移行で情報漏えいゼロを維持
大手金融機関では、PPAPを早期に廃止し、メールにファイルを添付すること自体を原則禁止とする方針を取っています。
これにより、誤送信・マルウェア感染といったインシデントを大幅に抑制。とくに三井住友フィナンシャルグループでは、全社員に対してファイル転送専用サービスの利用を義務付け、2022年以降の情報漏えい件数ゼロという成果を記録しています。
中堅製造業:クラウドストレージ併用で誤送信件数を80%削減
ある中堅製造業では、従来のPPAP運用から**「クラウドストレージ+アクセス制限+ファイル期限設定」**への移行を進めました。
その結果、社内・社外向けのファイル送信における「誤送信数」が導入前の月平均10件から2件へと減少し、約80%の削減に成功。従業員からも「モバイル端末での対応が楽になった」「パスワード管理のストレスがなくなった」といったポジティブな声が多く寄せられています。

脱PPAP導入ステップ
現状分析と影響範囲の洗い出し
まず最初に行うべきは、自社内でどのようにPPAPが使われているのかを可視化することです。どの部署が、どんな種類のファイルを、誰に向けて送っているのか。その使用頻度や業務影響を把握することで、導入すべき代替策が明確になります。
ツール選定とPoC(試験導入)
次に、候補となる転送サービスやオンラインストレージを比較・検討します。セキュリティ・利便性・費用のバランスを見ながら、自社の業務フローに合うものを選定しましょう。可能であれば一部部署でPoC(概念実証)を行い、現場の声を取り入れたうえで本格導入に進みます。
社内ルール策定・教育
ツールの導入と同時に、運用ルールの策定と従業員への教育が不可欠です。「どんなファイルをどの手段で送るか」「誰が責任者か」といったガイドラインを明文化し、社内研修やFAQ整備を行いましょう。
運用後のログ監査と改善
導入後も継続的にログを監視し、運用の問題点を洗い出すことが重要です。誤送信やヒューマンエラーの兆候を捉えて運用改善を繰り返すことで、実効性の高い「脱PPAP」が実現します。
まとめ――今すぐ始めるべき理由
PPAPはかつての“安全策”でしたが、現代のサイバーリスクにはもはや通用しない時代遅れの手法です。セキュリティ上の脆弱性に加え、業務効率の低下、法令対応や取引先の制約といった多方面の問題を抱えています。
すでに多くの企業・官公庁が「脱PPAP」を実践し、実際の効果も出ています。まずはファイル転送サービスの試用や、共有ルールの見直しから始めてみましょう。今こそ、より安全でスマートなファイル共有へ移行する絶好のタイミングです。
ネクストアライブでは、
「Next File Share」という次世代ファイル共有サービスを展開しています。
📌 Next File Shareの主な特長
✅ URLによるシンプルなファイル共有
✅ メールアドレス認証で安全にダウンロード
✅ 自動削除機能で誤送信・情報漏えいリスクを軽減
✅ ITスキルを問わない直感的なUI
✅ 月額500円からのリーズナブルな価格設定
気になった方は↓下記画像リンク↓より詳細資料をご参照ください。




