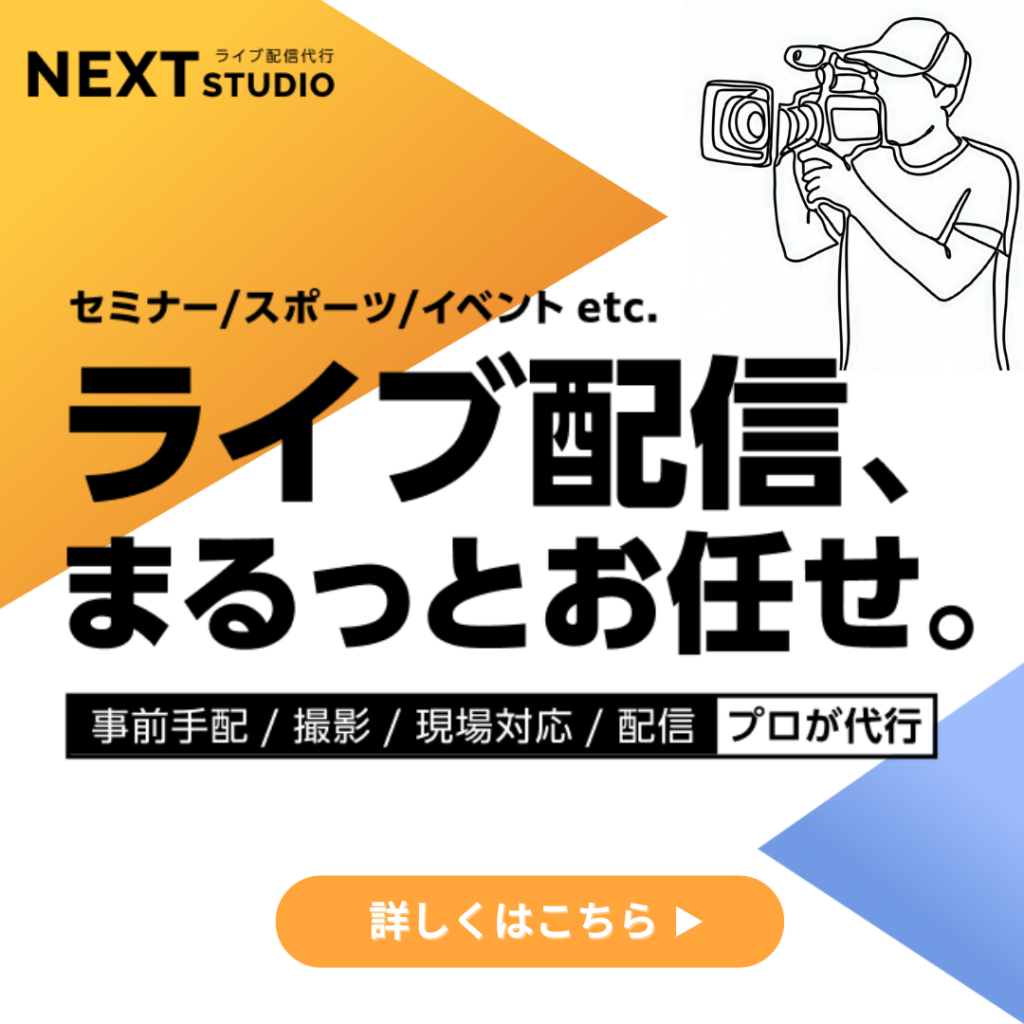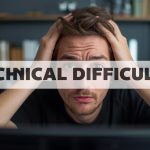ライブ配信は企業や学校、自治体など、さまざまな場面で活用されるようになりました。セミナーやイベント配信、教育現場での説明会や式典など、オンラインを通じて情報を届ける機会が増えています。その中で重要な要素となるのが「BGM(バックグラウンドミュージック)」です。音楽は配信の雰囲気を大きく左右し、視聴者の体験を高める一方で、著作権という法的リスクも伴います。本記事では、法人や教育機関がライブ配信でBGMを利用する際に知っておくべき実務的なポイントを、具体例やデータを交えて解説していきます。
ライブ配信について、詳しく知りたい方はこちらのブログ記事「ライブ配信とは?初心者でもわかる仕組み・活用事例・始め方を徹底解説」もぜひご覧ください。

ライブ配信におけるBGMの役割
視聴者体験を高める効果
BGMは視聴者にとって「雰囲気を感じ取る信号」のような役割を果たします。無音の配信では単調に感じやすく、視聴離脱の要因になることもあります。
調査によると、人は無音状態よりも音楽がある環境の方が集中力を持続しやすいとされ、特にゆったりとしたテンポの音楽はリラックス効果を高めることが報告されています。ライブ配信においても、待機画面や説明の合間にBGMを流すことで、視聴者が安心して視聴を続けやすくなります。
企業配信における利用シーン
企業のウェビナーや商品発表会では、オープニングや休憩中にBGMを取り入れることで、ブランドイメージを強調できます。たとえばAppleは新製品発表イベントで映像とともに音楽を効果的に組み合わせ、洗練されたブランド体験を提供してきました。規模の大小を問わず、音楽を演出に加えることで「伝えたいメッセージ」をより印象的に残すことができます。
教育機関での事例
学校や大学では、入学説明会や卒業式をライブ配信するケースが増えています。2020年以降、文部科学省の調査でも「式典のオンライン配信」が急増していることが報告されており、その際に使用されるBGMは「場の空気を整える」役割を果たしています。卒業証書授与のシーンに合ったBGMを流すことで、オンライン視聴者にも感動を共有してもらうことができます。
無音との比較
無音状態で進行する配信は、情報伝達には支障がなくても「空気感」が希薄になります。心理学の研究では「沈黙が長く続くと不安感や集中力の低下を招きやすい」とされており、BGMがあるだけで視聴体験の満足度が大きく変わるのです。したがって、BGMは単なる演出ではなく、視聴者に配信をポジティブに受け止めてもらうための重要な要素といえます。

~~~っぽい!~~みたいな雰囲気がする!
さてなぜそう思うのか。今まで生きてきた中での経験から、
BGMが自分の経験想起を脳で検知するんだよね。
だから、違和感を覚えさせるBGMはNG!
著作権の基本とBGM利用のリスク
音楽著作権の仕組み
音楽には「著作権」と「著作隣接権」という二つの権利が存在します。著作権は作詞者・作曲者など創作者に帰属し、著作隣接権は演奏者やレコード製作者に帰属します。ライブ配信で楽曲を使う場合、この両方の権利を侵害する可能性があるため注意が必要です。特に配信に関わるのは「公衆送信権」や「演奏権」と呼ばれる権利で、これらは著作権者の許可なしに利用することができません。
管理団体と申請の必要性
日本ではJASRACやNexToneといった管理団体が多くの楽曲を管理しています。例えばJASRACは国内外あわせて約500万曲以上を管理しており(2023年時点)、YouTubeやニコニコ動画などのプラットフォームと包括契約を結んでいます。これにより、個人が動画を投稿する場合は一定条件で利用が認められていますが、企業や学校が配信を行う場合には「商用利用」と見なされるケースが多く、別途申請や使用料の支払いが必要となることがあります。
違反が引き起こすリスク
無許可で楽曲を使用した場合、次のようなリスクが考えられます。
- 配信停止や動画削除:YouTubeやFacebookでは著作権侵害が検出されると自動的に配信が停止されることがあります。
- 損害賠償請求:著作権者や管理団体から使用料の請求や損害賠償を求められる可能性があります。実際に過去には、無断利用によって数十万円規模の賠償を求められた事例も報告されています。
- ブランドへの悪影響:企業や学校が著作権を軽視していると見なされると、社会的信用の低下につながりかねません。
企業配信における「商用利用」の解釈
著作権上の判断で重要なのは「商用利用にあたるかどうか」です。たとえ無料の配信であっても、企業や学校の宣伝・広報活動として行われる場合は商用利用に含まれると解釈されることが一般的です。例えば企業が新商品の説明会を配信する場合や、大学が入学希望者向けにオンライン説明会を行う場合は、営利活動とみなされ、著作権使用料の対象になることがあります。
リスク回避のために
これらのリスクを回避するためには、事前に楽曲の利用可否を確認することが欠かせません。JASRACやNexToneのデータベースで検索すれば、使用したい楽曲が管理されているかどうかを調べることができます。また、管理対象である場合には利用申請や使用料の支払いが必要です。特に法人によるライブ配信では「申請漏れ」が法的トラブルの大きな原因になりやすいため、社内でチェックフローを作ることが推奨されます。

配信で使用できる音源の種類と具体例
管理団体の許諾が必要な楽曲
まず大半の商業音楽は、JASRACやNexToneといった著作権管理団体が権利を管理しています。これらの楽曲をライブ配信で利用する場合は、事前に申請を行い、使用料を支払う必要があります。たとえばJASRACは「ネットワークでの利用に関する使用料規程」を設けており、視聴者数や配信時間に応じて使用料が決まります。教育機関の卒業式や企業の説明会などで有名な楽曲を使いたい場合は、必ず管理団体への確認が必要です。
著作権フリー音源(ロイヤリティフリーBGM)
もっとも実用的なのが「著作権フリー音源」の活用です。ここで注意したいのは、「著作権が存在しない」という意味ではなく、「一定の条件を満たせば自由に利用できるライセンスが設定されている」ということです。商用利用が可能なライセンスを選べば、法人や学校の配信にも安心して使えます。
代表的なサービスには以下のようなものがあります。
- YouTubeオーディオライブラリ
無料で利用でき、商用利用も可能な楽曲が多数公開されています。ジャンルやムード別に検索でき、著作権リスクが低いのが特徴です。 - DOVA-SYNDROME
日本発の人気フリーBGMサイト。利用規約に従えば商用配信にも使えます。実際に企業の動画制作や教育機関の配信で多く利用されています。 - Audiostock
有料の音楽素材マーケットプレイスで、商用利用を前提としたBGMが揃っています。月額プランを契約すれば法人利用も容易で、ライブ配信に適した曲が充実しています。
実際の利用事例
教育機関では、卒業式や学校説明会をオンライン配信する際に、DOVA-SYNDROMEやAudiostockの楽曲を利用する事例が増えています。ある私立高校では、式典映像にフリーBGMを組み合わせることで「無音による違和感」を解消しつつ、著作権の問題を回避しました。
また、企業のウェビナーではAudiostockの定額プランを導入し、毎回の配信で安心してBGMを活用できる仕組みを構築している事例もあります。
ライセンス確認の重要性
フリー音源を利用する際には、必ず利用規約やライセンス条件を確認する必要があります。例えば「商用利用可」とされていても、改変や再配布が禁止されている場合があります。また、一部の音源では「クレジット表記(作曲者名の明記)」を求められることもあります。
特に法人利用の場合は、配信前に次の点を確認しておくと安心です。
- 商用利用が許可されているか
- 配信プラットフォームでの利用が明記されているか
- クレジット表記の必要有無
- 動画アーカイブとして残す場合も利用可能か
公共領域(パブリックドメイン)音楽
著作権が消滅した古典的な楽曲(例:ベートーヴェンやモーツァルトの作品)は自由に利用できます。ただし、演奏や録音には「著作隣接権」が存在するため、市販CDの音源をそのまま使うことはできません。代わりに、権利フリーとして公開されている演奏データを利用するのが安全です。

例えばYoutubeライブで配信をしたとき、オープニングで使用した曲が
規約に抵触して、アーカイブとなった時に無音処理がされてしまったんだ。
最近はAIを使って検知もするようになってる。特に気を付けよう。
企業・教育機関が注意すべき著作権上のポイント
個人配信との違い
個人の趣味で行うライブ配信と、企業や教育機関が行う配信では、著作権の扱いに大きな違いがあります。特に法人による配信は「商用利用」とみなされる可能性が高く、利用条件や申請の必要性が厳しくなります。たとえ無料で視聴できるイベントであっても、企業の広報活動や学校の募集活動に直結する場合は営利性があると判断されるケースが一般的です。
配信プラットフォームの規約
YouTubeやZoom、Teamsなどの配信プラットフォームは、それぞれ独自の規約を設けています。YouTubeはJASRACやNexToneと包括契約を結んでいますが、それは主に「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」が対象です。法人が公式チャンネルで配信する場合や、有料イベントとして開催する場合には、この包括契約の範囲外となる可能性があります。ZoomやTeamsに関しても、BGMを流す行為は権利者の許諾が必要とされる場合が多いため、事前確認が欠かせません。
学校行事配信のケース
学校が文化祭や卒業式を配信する場合、演奏される合唱曲やBGMが著作権管理楽曲であれば、使用許可が必要になります。文部科学省は2020年以降のガイドラインで「学校行事のオンライン配信においても著作権法の適用を受ける」と明示しており、教育機関だからといって特例的に自由利用できるわけではありません。実際に、卒業式のオンライン配信で無断使用したBGMが著作権侵害と指摘され、アーカイブを削除せざるを得なかった事例もあります。
商用ウェビナーでの留意点
企業がウェビナーや製品発表会を行う際は、必ず「使用楽曲の権利状態」を確認する必要があります。特にオープニングやクロージングで人気楽曲を使うとブランド感は高まりますが、無許可利用は大きなリスクです。安全に行うためには、商用利用可能なフリー音源や有料BGMサービスを契約し、定常的に利用できる仕組みを整えることが推奨されます。
内部利用と外部公開の違い
社内研修や社内イベントのように「内部限定配信」の場合でも注意が必要です。閉じた環境であっても、録画データを後日外部公開するケースが多く、その際に著作権侵害が発生する可能性があります。内部利用だから大丈夫と安易に考えるのではなく、最初から「将来の公開リスク」を想定した楽曲選びが重要です。

BGM利用を安全に行うための実務フロー
配信前に確認すべきチェックリスト
BGMを安全に利用するためには、事前の確認が欠かせません。以下のチェックリストを配信準備の段階で確認しておくと安心です。
- 使用予定楽曲が著作権管理団体の管理下にあるか調べる
- 管理下にある場合、利用申請や使用料支払いの必要有無を確認する
- フリー音源の場合は利用規約を熟読し、商用利用可否を確かめる
- クレジット表記の必要性やアーカイブ利用可否を確認する
これらを怠ると、配信中断や動画削除などのトラブルに直結します。
社内ルールの整備
法人や教育機関では、担当者ごとに判断がばらつかないよう、社内ルールを定めておくことが重要です。たとえば「利用可能なBGMサイトのリストを共有する」「配信前に法務部門が確認するフローを作る」など、具体的な運用ルールを整備することで、リスクを最小化できます。
チーム内での役割分担
ライブ配信は複数の担当者が関わることが多いため、BGMに関するチェックを誰が行うか明確にしておく必要があります。例えば、配信オペレーターは技術面を担い、法務担当が著作権チェックを行う、といった形で分担するのが理想です。これにより「うっかり無断使用してしまった」というミスを防げます。
トラブル発生時の対応策
万が一、配信中に著作権侵害が指摘された場合は、速やかに配信を停止し、権利者に連絡することが求められます。その際、使用楽曲の出所や利用規約を記録として残しておくと、対応がスムーズになります。
まとめ
ライブ配信におけるBGMは、視聴者体験を向上させる大切な要素ですが、同時に著作権リスクが伴います。特に企業や教育機関による配信では「商用利用」とみなされることが多く、個人配信よりも厳格な対応が必要です。
安全に運用するためには、管理団体の楽曲利用ルールを把握し、商用利用可能なフリー音源や有料BGMサービスを活用するのが効果的です。また、社内にチェックフローを整備し、利用規約を遵守することで、安心して質の高い配信を実現できます。著作権に配慮したBGMの活用が、視聴者にとっても配信者にとってもメリットをもたらすのです。
ライブ配信をしてみたいけど、、、、、
なにから手を付ければいいかわからない、、、
何が必要なの?どこでやればいいの?
やりたいんだけど!!!できない!!!
という方は、私たちにお任せください!
全て解決できます。
詳しくはこちらをクリック↓↓