ライブ配信は、企業や学校、自治体にとって「情報発信」「ブランド強化」「教育活動」の重要な手段となっています。YouTube Live や Zoom ウェビナー、Instagram Live などのプラットフォームを通じて、リアルタイムで双方向コミュニケーションを取れる点は大きな魅力です。
しかし、その一方で不用意な発言や不適切な表現は、炎上・信頼失墜・法令違反につながるリスクをはらんでいます。実際に、配信中の不適切発言が原因で番組スポンサーが撤退したり、学校配信で生徒の個人情報が漏洩して大きな問題に発展したケースもあります。
特に組織として行う配信では、個人の失言が「組織全体の信用問題」に直結します。本記事では、公式ライブ配信で避けるべきNGワードとその理由、組織的な対策方法、そして万が一問題が起きた際の対応策について、事例を交えながら解説します。
ライブ配信について、詳しく知りたい方はこちらのブログ記事「ライブ配信とは?初心者でもわかる仕組み・活用事例・始め方を徹底解説」もぜひご覧ください。

公式ライブ配信でNGワードが問題になる理由
ライブ配信は視聴者にとって「公式な発信」として受け止められます。企業が発する言葉には、次のような理由から強い社会的責任が伴います。
法令遵守・プラットフォーム規約の存在
YouTube をはじめとする主要プラットフォームには コミュニティガイドライン が設けられています。例えば YouTube の規約では「差別的な発言」「ヘイトスピーチ」「誤情報の拡散」などが禁止されています【参考:Googleサポート】。これに違反すると、動画削除だけでなく アカウント停止 に至る場合もあります。実際、2022年には誤情報拡散を理由にいくつかのチャンネルが停止措置を受けました。
信用失墜とブランドへの影響
企業の公式配信での失言は、個人配信の炎上以上に大きなダメージを与えます。例えば国内のあるメーカーでは、広報担当者が製品発表ライブで不適切な冗談を口にし、SNS上で炎上。結果的に数日で数千件の批判投稿が寄せられ、最終的に公式謝罪と動画削除に追い込まれました。
教育・公共性を担う立場の責任
学校や自治体の配信は、教育的・公共的な性質を持ちます。誤った発言や差別的表現が含まれれば、教育機関としての信頼や行政への市民の信頼が損なわれます。過去には地方自治体のオンライン説明会で、担当者の不用意な発言が報道され、謝罪会見に発展した事例もありました。

ライブ配信をするという事の意味も考えよう。
映像を通じて世の中に出る。発信するということを。
組織配信で避けるべきNGワードのカテゴリー
公式ライブ配信では、単なる「言葉の選び間違い」が企業や学校のブランドを揺るがす大きなリスクになり得ます。以下では、特に避けるべきNGワードや表現をカテゴリーごとに解説します。
差別・ハラスメント発言
人種、性別、宗教、国籍、障がいなどに関する差別的な発言は、最も深刻なトラブルにつながります。YouTubeやTikTokなど主要プラットフォームは、ヘイトスピーチ禁止を規約に明記しています。
例:
- 「女性には無理だ」などの性差別的な発言
- 「○○人はこうだから」といったステレオタイプの表現
国内でも、芸能人の生配信で差別的な冗談を発言し炎上、スポンサー契約打ち切りに至ったケースがあります。企業や学校が同様の失言をすれば、コンプライアンス違反として重大な処分に直結する可能性が高いです。
政治・宗教などセンシティブな発言
組織配信では特定の政治的立場や宗教的価値観に偏った発言は避けるべきです。公的機関や学校での発言は「中立性」が求められるため、発言者の個人的な意見であっても公式見解と受け取られかねません。
例:
- 政治家や政党への賛否を強調する発言
- 宗教儀礼や思想を揶揄する表現
実際に海外の教育機関では、配信授業中に特定の宗教を否定する発言があり、数日で数百件以上の抗議を受けて謝罪に至った事例もあります。
暴力・違法行為を連想させる表現
暴力的な発言や犯罪行為を肯定するような表現は、社会的責任に反する危険な言葉です。YouTubeやFacebookでは「危険行為の助長」も厳しく禁止されています。
例:
- 「未成年でも飲んでいいんじゃない?」といった違法行為を容認する発言
- 暴力や武器に関する不用意な冗談
過去には配信者が「危険なチャレンジ企画」を紹介してアカウント停止となったケースもあり、組織配信で同様の発言をすれば、法的問題や損害賠償請求に発展する可能性も否定できません。
誤情報・虚偽の説明
特に教育機関や自治体の配信で注意すべきなのが「誤情報の発信」です。新型コロナウイルス流行時には、誤った医療情報を含む発信がSNSで拡散され、多くの公式チャンネルが非難の対象となりました。
例:
- 科学的根拠のない健康法や医療情報を断定的に述べる
- 企業製品について根拠のない性能誇張をする
情報の信頼性を担保することは、公式配信における最大の責任の一つです。
個人情報・守秘義務違反につながる発言
配信中に社員や生徒の名前、住所、連絡先などを不用意に口にしてしまうのもNGです。学校配信では生徒のプライバシーが侵害される可能性があり、企業では顧客情報の漏洩が重大なコンプライアンス違反となります。
実際に教育機関でのオンライン授業配信中に、生徒の個人情報が画面に映り込んでしまい、保護者から強い抗議を受けた事例があります。

配信をするときは、自分の顔に企業のロゴが
貼り付けられているつもりで取り組むんだ。
NGワードを避けるための組織的対策
公式ライブ配信は、担当者一人の努力だけでは安全性を確保できません。組織全体としての仕組みを整えることが、NGワードによるトラブルを防ぐ最も効果的な方法です。以下では、実務に直結する具体的な対策を紹介します。
配信前の台本・チェック体制
事前にシナリオや台本を準備し、複数部署で内容をチェックすることが重要です。特に企業では広報部門と法務部門、学校では教務・生徒指導担当を巻き込み、発言内容に不適切な表現が含まれていないかを確認します。
実際、国内の大手メーカーでは製品発表配信の台本を広報と法務で二重チェックする運用を導入し、炎上リスクを大幅に軽減しています。
ガイドラインの策定
「どんな言葉を使ってはいけないか」を社内マニュアル化し、配信に関わる全員に共有しておくことが大切です。
例:
- 差別的表現禁止リスト
- 個人情報を含む発言禁止ルール
- 政治・宗教に関するコメント制限
YouTubeなどの公式ガイドラインをベースに、自組織の業種・活動内容に合わせたガイドラインを策定すると効果的です。
モデレーター配置によるコメント管理
ライブ配信では視聴者コメントもリスク要因です。差別的・誹謗中傷的なコメントがそのまま流れると、配信者だけでなく組織のイメージまで損ないます。
そのため、モデレーター(管理者)を必ず配置し、問題コメントを即時非表示にする仕組みを作りましょう。YouTube Live や Facebook Live にはモデレーション機能が備わっており、事前にNGワードをフィルタリングすることも可能です。
研修・リハーサルの実施
出演者や担当者に対して、配信マナー研修を実施することも効果的です。特に学校では、生徒が出演する場合に「発言してはいけない言葉」をあらかじめ伝えておく必要があります。
また、リハーサルを通じて発言チェックを行うことで、本番中の想定外の発言を減らすことができます。
外部事例から学ぶ
炎上やトラブルを経験した他組織の事例は、貴重な教材となります。例えば地下アイドルグループの配信で、ファンへの不適切な発言が拡散され炎上したケースがあります。こうした事例を組織内で共有することで、「うちは大丈夫」という油断をなくし、配信全体の意識を高められます。
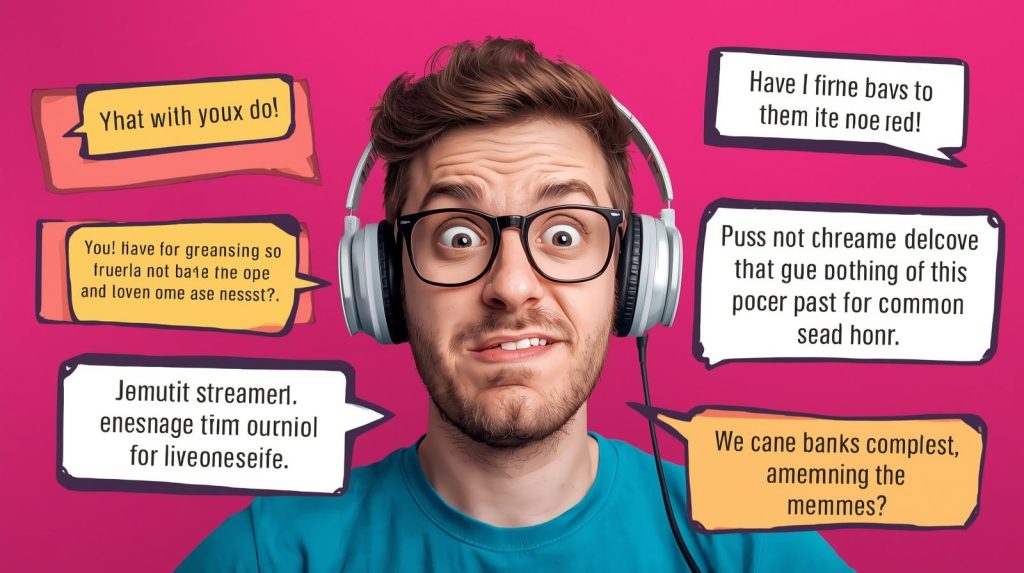
万一NG発言をしてしまった場合の対応
どれだけ注意しても、配信中に思わぬ失言やNGワードが出てしまう可能性はゼロではありません。大切なのは、起きてしまった後の初動対応です。迅速かつ誠実な行動によって、信頼を大きく損なう前に被害を最小限に抑えることができます。
即時の訂正・謝罪
発言直後に気づいた場合は、その場で訂正・謝罪を行うことが最も効果的です。配信を視聴している人に対し、「先ほどの発言は不適切でした。誤りを訂正しお詫びいたします」と明言することで、炎上の拡大を防げます。
アーカイブの非公開・編集対応
配信が終了した後は、問題のある部分を含むアーカイブを速やかに非公開にすることが重要です。そのうえで、必要に応じて編集を行い、修正済みバージョンを公開するか、完全に削除するかを判断します。
実際に国内の企業公式チャンネルでも、広報担当者の不適切発言を含むアーカイブを即日削除し、翌日に公式声明を出したことで、大きな炎上を回避した事例があります。
公式声明・広報対応
企業や学校といった組織の場合、個人の謝罪だけでは不十分です。公式HPやSNSアカウントを通じて「組織としての謝罪声明」を発表することが求められます。
この際、「事実関係の説明」「発言が不適切であったことの認識」「再発防止策」を明記することが信頼回復の第一歩となります。
関係者への説明責任
学校であれば保護者、企業であれば取引先やスポンサー、自治体であれば市民への説明責任があります。直接的に影響を受ける関係者には、個別にメールや文書で説明を行い、誠意を示すことが重要です。
例えばある大学では、配信授業中の教員発言に対して抗議が殺到した際、学長名で保護者と学生に向けた謝罪文を即日配布し、対応の速さが信頼回復につながったと報告されています。
まとめ
企業や学校、自治体が行う公式ライブ配信は、単なる情報発信にとどまらず、組織の信頼やブランド価値そのものを映し出す場です。NGワードや不適切な発言は、一瞬でその信頼を損なう可能性があります。
今回解説したように、差別的な発言や誤情報、個人情報の漏洩などは特にリスクが大きく、炎上や信用失墜、場合によっては法的問題に発展することもあります。
しかし、事前の台本チェックやガイドラインの策定、モデレーターの配置、研修やリハーサルといった組織的な仕組みづくりを行えば、多くのリスクを未然に防ぐことができます。また、万が一問題が発生しても、迅速かつ誠実に対応することで信頼回復につなげることが可能です。
公式配信は、正しく運営すれば大きな信頼を築く強力なツールです。NGワード対策を徹底し、安全で健全なライブ配信を行うことが、持続的なブランド発信の基盤となるでしょう。
ライブ配信をしてみたいけど、、、、、
なにから手を付ければいいかわからない、、、
何が必要なの?どこでやればいいの?
やりたいんだけど!!!できない!!!
という方は、私たちにお任せください!
全て解決できます。
詳しくはこちらをクリック↓↓
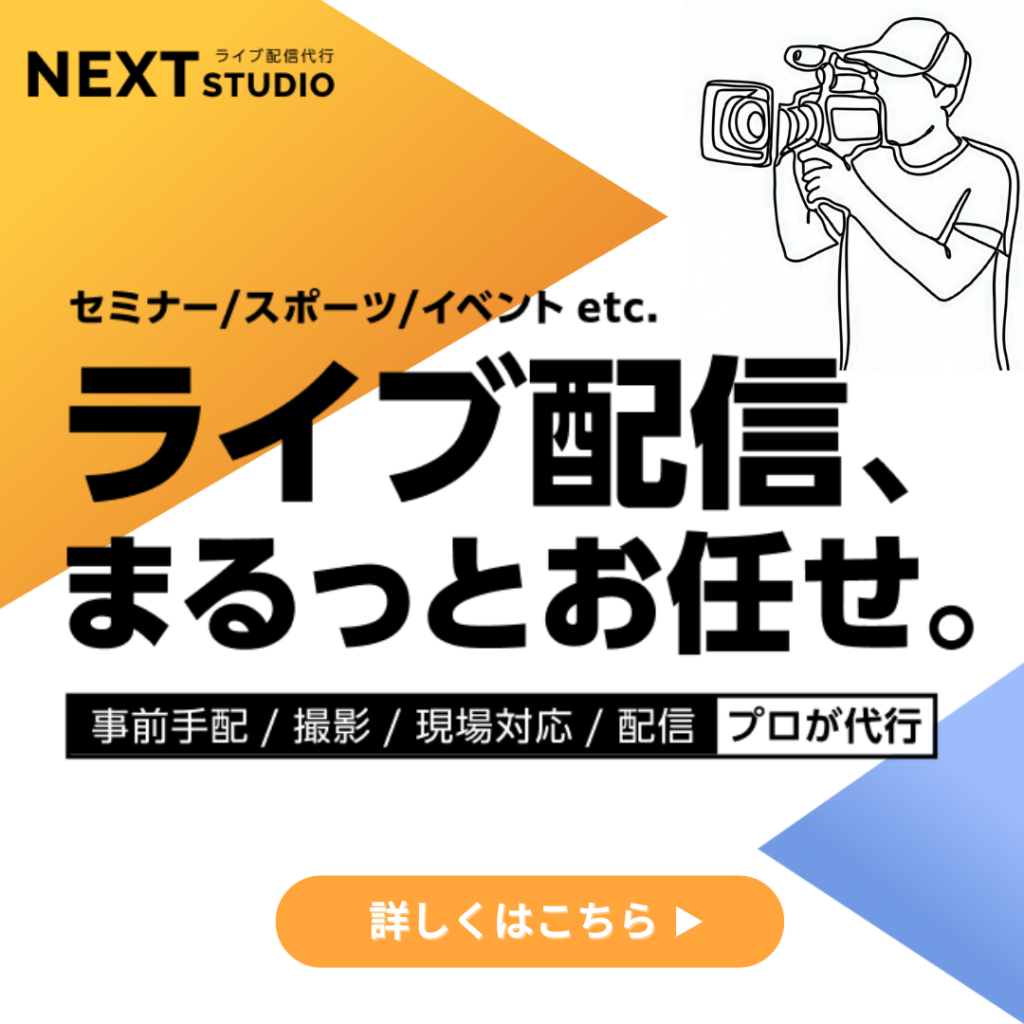

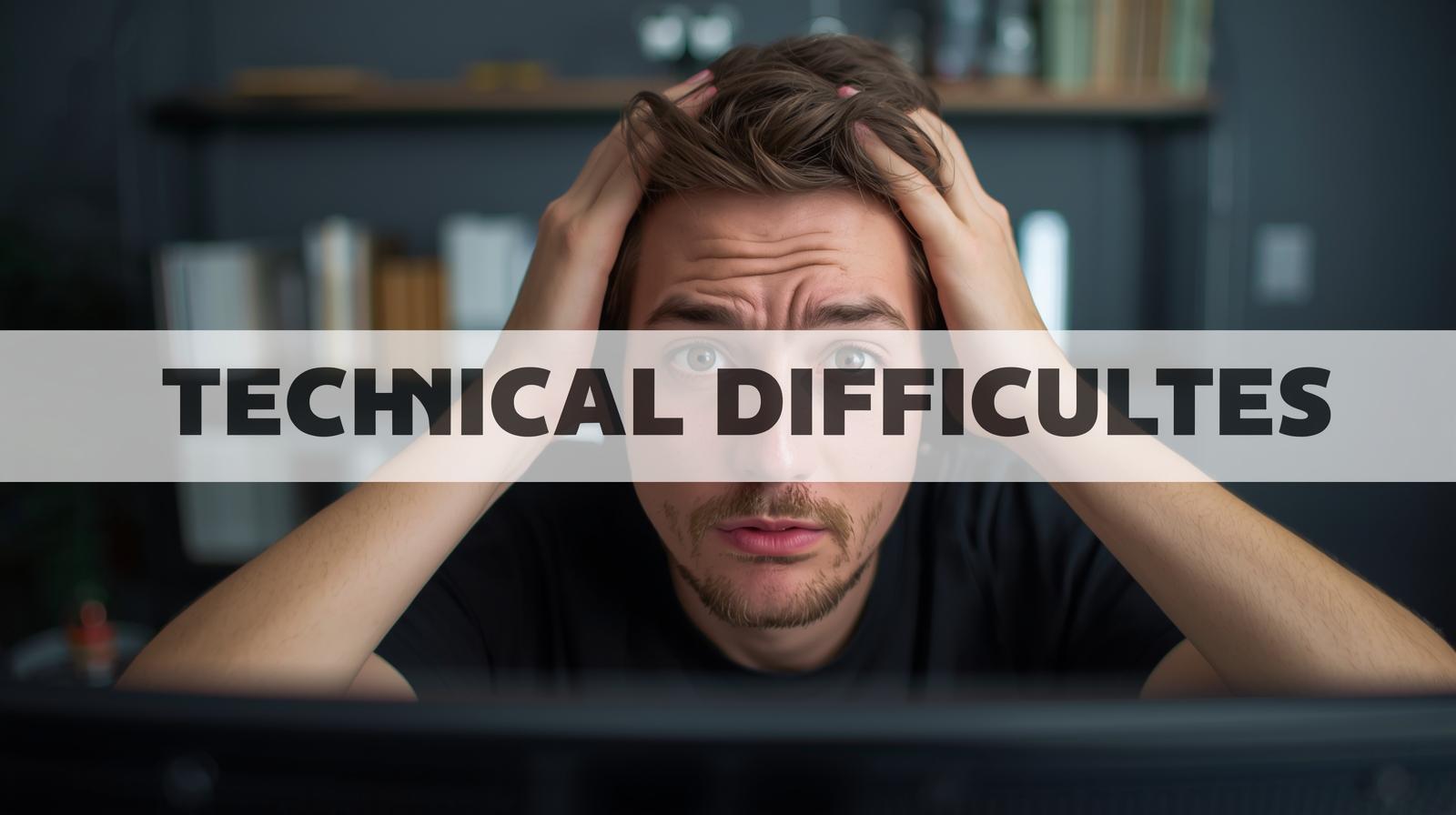

で変換されているような画像-1-150x150.jpg)